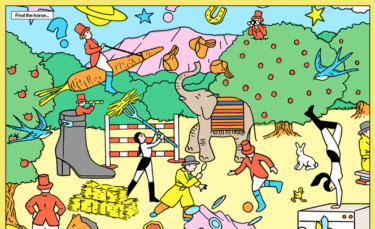Fondazione Prada|“LIZZIE FITCH / RYAN TRECARTIN: IT WAIVES BACK”から見る、ありのままの事実と真実

Photo: Courtesy of PRADA
「PRADA」財団の支援のもと「Lizzie Fitch / Ryan Trecartin: It Waives Back」展がPRADA Aoyamaにて開催。2024年10月24日〜2025年1月13日の会期に先駆けて10月23日にはアーティストトークが開催された。
本展は、米国のアーティスト、リジー・フィッチとライアン・トレカーティンによる日本初個展。ともにオハイオ州アセンズを生活、活動の拠点としており、2000年にロードアイランド・スクール・オブ・デザインで出会って以来、共同で活動。ノンリニア映像と没入型インスタレーションを融合する協業活動で高い評価を得ており、過去の作品はこれまでホイットニー美術館やMoMAPS1、パリ市立近代美術館、ヴェネチア・ビエンナーレ、クンストヴェルケ現代美術センター、アストラップ・ファーンリー美術館、「PRADA」財団で展示。


Photo: Courtesy of PRADA
上映される映像作品は各々の固有のアイデアを異なる形で捉えている。例えば、映画『TITLE WAIVE』では、時間が作品の中心的な要素となっている。2017年から2024年の間に撮影された映像を使い、登場人物や背景、場面の継続した広がりを描いている。時間もナラティブを形成し編集に影響するという役割を担っている。この創作過程は、移り変わるナラティブが如何に時間という枠組みを破綻させたり、回復させたりするかを物語ると同時に、リジーとライアンが記憶と時間を“ひとつながりの生きた存在”として体験していることを強調している。もう1つの映画『Waives Back(Whether Line)』では、シーン毎に実写とアニメーションのトランジションを組み合わせている。長年のコラボレーターであり、3Dモデリング、アニメーション、建築と幅広く手がけるレット・ラルーが作成したこれらのシークエンスは、オハイオ州にあるアーティストの所有地と常設セットの様々な様子を使って、シーンをプロット内の点ではなく、地図の地形として位置付けている。



Photo: Courtesy of PRADA
目的を成し遂げられるために、時間をコンセプトに、まるで地図を描くような緻密な論理で二人の作品は成立している。つまりそれはこの世界における事実と真実で構成されたありのままの現実を拡張させる表現ともいえる。
それらは映像にも反映されている。二人はすでにあらゆるテクノロジーをインサートしており、それはこの広範囲に及ぶ作品やそのスケールから感じ取れるはず。今回の展示には制限という観点もあり、自然と都市、退廃と進化、近眼と遠眼といった質実剛健による境界線や政治に関しても言及されている。
音楽や詩の音色も重要なファクター。詩はどのような文化的背景があろうともある種の誠実さやフォーマルを保ち、意味を成している。それは重なり合うことでまるでボディーランゲージのように鑑賞者の眼の前でジェスチャーを印付ける。「外」の傍観者からすると、米国人の背景にある観念、文化、政治、都市や地域に対する行動規範が見え隠れして興味深い。それこそが彼らの創作道徳であり、アティチュードなのだろう。新作である「フィギュラティブミザンセーヌ(比喩的舞台演出)」として構成された『彫刻的劇場』にはそれらが取り入れられ、ある特定の文化に対して反故にする者がいれば、そこには存在しないとも捉えることができる。


Photo: Courtesy of PRADA
リジー・フィッチは展示に関して、「我々は2017年から多くの撮影をこなしてきました。いつも考えているのはそれがベースとなっているということです。その中で、これまでの作品を見返すという行為はアイデアの一つ。実際に振り返り、どういう作品でどういう意味があり、何を示しているのか、を認識するところから始まりました。それは、距離のあるところから戻ってくるという観点であり、ホラー的な要素、違う奇妙さも感じ取ることができると思ったのです」と語っている。一方で、ライアン・トレカーティンはWaivesという言語を創作に落とし込んだことは「創作の起点の一つとなっていた」と語っている。「Waives(Waves)という語呂は波という意や、手を振るといったジェスチャーに纏わる意味があるし、(権利を)放棄する、といった意味もあったり、多元的な解釈ができる。『彫刻的劇場』にあらゆるサウンドを溶け合わせ、一種の(静かなる)錯乱を呼び起こさせるのは、そういった狙いがあります。展示の主題も同様のことを踏まえました。まるでジャックするような感覚です」。
過去(の作品)に回帰し、素材として再編集する。それはつまり時間の役割の見直しとも捉えることができる。それについて、トレカーティンは「時間的な距離でいえば、遠隔から至近までさまざまな距離で見ているから。例えば政治的な緊張感のある時期に、特に我々のような南西部で生きていると、どういうことが起きているのだろうと想像を働かせます。土地に対するイメージだけではなく、人間のキャラクター性(ルーツやアイデンティティー)に対する見解など無数のイメージを交差させることで、最終的には新たな観点が生まれるという見方もできるのではないでしょうか。我々の映像作品に登場するキャラクターは持ち得た能力を使って、イメージを手がかりに行動を変えていくことで、物語も変わる。それはテクノロジー的にいえば、パストコードを変えることでもあります。それは記憶とも似ているので、記憶が変わることだってあるのです」と語っている。


Photo: Courtesy of PRADA
彼らの好奇の眼はどこに向けているのだろうか。それは、現行の物語に対する捉え方やメディアの定義に関する提示である。この思考は「PRADA」財団が世界中で開催されているプロジェクトを通して一貫して取り組んできた態度と通ずる。未来のストーリーテーリングであり、考察でもある。トレカーティンは「ストーリーに対する不安に似通った恐怖心があるからこそ、情報やデータが優先されるのが現代。個人的にはそのような世界に住みたいとは思わないし、ホラーをホラーとして認識していないので、その潜在的な感覚も作品に反映させています」という個人的な観点を口にしていた。他方でフィッチは、より社会的な観点で捉えている。「今回の展示ではレンダリングを使用することで、さまざまなシュミレーションを視覚化させています。シュミレーションが現実に侵略していく方法論が、後から発生していく。AIモデルを人格化させたのもそういう意図があります」。

Photo: Courtesy of PRADA
また、サウンドデザインは新作全体の主役とも呼べる存在。トレカーティンが作曲し、2024年8月にコロラド州アスペンでライブレコーディングした音楽が、映画の随所に挿入されている。音楽とライブパフォーマンスは、トレカーティンとフィッチの芸術活動の基礎をなす要素であり、彼らはデジタル音楽制作ソフトウェアを活用して膨大なサウンドトラックを作成、分解、再構築し、その多くをその彫刻的劇場や映画に取り入れている。それに触れることで、生活と作品、共同作業などのプロセスが重なり合うかのよう。それは二人が今現在に焦点を当て、それを踏まえて生きている証でもある。二人は口を揃えてこう話す。「今生きている思い出を共有しています。だから、過去系や未来系の話も現在系で話されています。この映像の中では汚染に対しての定義を暗示させ、それにはアイデンティティも内包している」。
社会の枠組みや制度が持つ何かを生み出す力やその限界と不安に関する考察は、鑑賞者が五感で感じるあらゆる反応に込められている。

Photo: Courtesy of PRADA
「LIZZIE FITCH | RYAN TRECARTIN: IT WAIVES BACK」
会期:2024年10月24日(木)~2025年1月13日(月)
場所: PRADA Aoyama 6F
東京都港区南青山 5-2-6
入場料無料