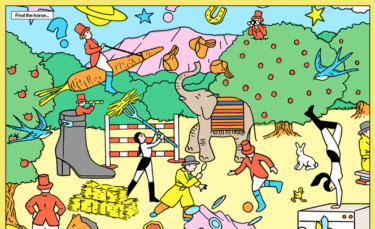AW2024-25 PARIS MENS|日爪の意図した衣鉢の美学に触れ、気づかされたグレースの多元的なグラデーション

Wales Bonner AW2024-25 Photo: Courtesy of Wales Bonner
2023年6月より、欧州での取材を再開した。その取材を下敷きにしたQUOTATION FASHION ISSUE SS24 vol.39が2月27日に発行となる。その2024年春夏パリメンズではFête de la Musique(音楽の日)の週だからか、街行く人たちは陽気でありながら、憂いのある馴染み深い様子であった。しかし2024年1月、ロワシー=シャルル・ド・ゴール国際空港に到着すると、(気のせいなのかもしれないが)気配の違いを感じ取った。
まず、至る所で行なわれている修繕、改修、設営。これは昨年も行なわれていたが、2024年7月26日から8月11日までの17日間、此処パリで開催されるパリ五輪の影響だろう。だが、完成とは程遠い箇所が多く見受けられ、住民からは果たして間に合うのか、などという声も聞こえてくる。また、パンデミック後における経済不況も影響しているとも考えられる。以前から街中で見かけた物乞いは更に目立つようになり、人々もどこか苛立っているのが異国人であっても気がつく。

パリ市内の様子、ファッションウイーク中は生憎の天気が続いていた
そういった街中で通例通り開催されるファッションウイーク。初日のオープニングを飾った「ブルク アクヨル」のコレクションノートにはスタジオ・ベルソーの廃校とブルク・アクヨルの恩師の逝去について触れられていた。スタジオ・ベルソーは1954年にスザンヌ・ベルソーがファッションデザインコースとして設立、1970年からはマリー・ルッキによってファッションデザインとパターン製作の専門学校として運営され、イザベル・マランやマルティーヌ・シットボンなどを輩出。IFM(Institut Français de la Mode)と並ぶパリを代表するモード専門学校である。そのベルソーには多くの日本人留学生もいたという。このようなフランス、パリの現状とそこで創作に向かうことに関して話を聞ける人物は一人しかいないと考えた。今回の取材の際に、合間を縫って必ず会いたいと思っていた稀代のModistである。

日爪ノブキのアトリエの外観
パリを拠点とする帽子職人、日爪ノブキは文化服装学院を首席で卒業後、単身イタリアへ渡り、コレクションを発表。国内外の舞台やアーチストの帽子やヘッドピースを製作。同時に自身の名NOBUYUKI HIZUMEとしてアーチスト活動を開始。2009年よりフランスに拠点を移し、「ディオール」「ロエベ」といったメゾンのヘッドピースやガーメントを手がける。そして2019年に若干39歳で日本人として唯一の「Modist(=婦人帽製造工)」としてのMOFを授賞し、同年「ヒヅメ」を開始。
実は何度か顔を合わせたことがあったが、他ブランドのイベント中であったため、声をかけずこの日を待ち侘びていた。アポイントの時間に指定された住所に着くと、そこはパリ11区シャロンヌ通りにある物珍しい外観を持つ壮大な工業用中庭。エッフェル塔を設計したフランスの建築技師、ギュスターヴ・エッフェルによって手がけられた工房。鋳鉄製の構造は、当時の建築様式を呼び起こし、コの字型の5つのフロアに広がる作業場には通路が設けられており、赤く塗られた金属フレーム、伝統的なレンガの黄土色、木製の要素が幸せなモノクロカラーで組み合わされている。現在はオフィス、ダンススタジオ、ヨガルーム、演技教室、建築会社、さらには旅行代理店が入っていて、その一室が日爪のアトリエとなっている。「ここはパリ市管轄なので、窓さえ勝手に修繕することができません。SDGsに積極的な街なので、そういった環境保護などの理由があれば変更できるかもしれませんね」と日爪は話し始め、冒頭で語ったこの街に対する現在の印象についても概ね同意してくれた。

アトリエの様子
「確かに不穏な空気は漂っています。在住の僕でさえ、メトロ(地下鉄)に乗ることを少し躊躇するくらいですから。ただ、ファッションウイークは現行通り開催されていますね。それはこの国にとってモードがどういう存在なのか、を物語っている証でもあると思います」。日爪は現在「ヒヅメ」の最新コレクションを制作する傍ら、或るメゾンの作品群のガーメントを制作しているという。「自身のブランドをやりながら、メゾンの仕事をさせてもらえることは僕にしかできない働き方だと自負しています。メゾンといっても巨大企業なので、アイデアから完成形まで事細かに指定があると思われますが、全く違います。思案してものが採用されると、『どうすればノブキの案(サブジェクト)は形(オブジェクト)になるの?』とその全てを任せてくれるのです。ある時代からディレクター職というある種の眼と選択がそのブランドの舵取りとして重要になってきて、現在ではそれが主流となっています。僕が一緒に仕事をしているメゾンのトップディレクター、その傘下にいる各部門を統括するキーパーソンの審美眼と選択力には驚かされるばかりです」と語る日爪は、3月に発表する自身のコレクションと、パリウィメンズで発表するメゾンのガーメントの納品に向けて、これから佳境に入るという。
一方で、「僕は現在44歳ですが、若い頃に出会った欧州の同世代の友人たちが頭角を現してきて、メゾンの一部門を任せられている人も多い。地に足をつけて創作に向かってきた人たちなので、その中で働ける喜びがあります。西洋の人たちと親密な対話、創造的な集合を生むまでに時間がかかるのです。だからこそ、日本には帰れないとも思っています。そう、後には引けない状況を自らが望んで作ったのです。先ほど話していたスタジオ・ベルソーの日本人留学生たちも高い志を持ってパリまで来ていたと思います。ただ、あくまでも異邦人なのです。全員がそうとはいいませんが、この街でなくてもベルソーで勉強したという実績を持ち帰って日本で就職すれば良いという構えがどこかしらにあったのではないでしょうか。この街でモードに携わることがどういうことなのか。生活、文化に真の意味で溶け込むか、もしくは徹底して自らの世界観を作り上げるか。僕はどちらも捨てがたく、今も尚その両軸を探究しています。そのためにもフランスだけではなく西洋全体のことを真に理解していなくてはなりません。今パリで発表する日本のブランドは多いですが、その挑戦に対してリスペクトがあります」とも。

アトリエ内にある「ヒヅメ」の最新コレクションのサンプル
この数年、パリでショーだけではなく、展示会をする日本のブランドが圧倒的に増えたことは自明の理である。日爪の話は目から鱗が落ちるかのようで、何故この地で発表を続けるのか、日本での発表を続ける選択を取らなかったのか。結局ファッションはデザイナーの「視座」と「自我」の結実である。現地で取材をしていると改めて痛感する。ここはパリである、と。偉大なアーカイブを擁するメゾンが数多あるパリである。デザイナーは先達が残した歴史と文化と対峙しなければならない。この街が擁護してきた規範とデザイナーの独自性との葛藤が、程度の差こそあれ、生じるはずである。受動的に影響を受けてしまうことを警戒しすぎるあまり、その格式が微塵も表現されない場合もあるだろう。
ただその文化や歴史に脈々と受け継がれていく「スタイル」から刺激と着想を吸収した後、その成果がアーカイブから遠くなればなるほど、そのデザイナーの才覚は優れているといえるのかもしれない。それはメゾンだけではなく、人種や民族、宗教そのものが持つアーカイブに接する時、畏敬の念や思い入れが過度に強すぎると、却って存分に発揮できないこともあるだろう。従って、出来るだけクールに、先達の「スタイル」と距離を置きつつ、「いま」を感じさせる正確な判断がデザイナーには求められる。それが自信に満ちた独創の「視座」であり「自我」である。日爪はそれを持ち得え始めているのだろうし、だからこそ安全圏から脱却し、固有の探究を続けているのであろう。異なる息吹であるが、そのような面構えをパリメンズで感じさせたブランドが「ウェールズ ボナー」である。



Wales Bonner AW2024-25 SHOW VENUE National Conservatory of Arts and Crafts
1月17日、場所は1794年に設立されたフランス国立工芸院。ここは継続的な研究環境を提供し、科学技術と確信に纏わる基礎から応用までのあらゆる研究をサポートし、科学や科学技術の文化保全に大きく貢献している特別高等教育機関として、世界中の専門学生を支持している。招待客の座席は「Horizon」「River」「Cairo」というエリアに分かれており、そういった細部にも世界観を体現しようというグレース・ウェールズ・ボナーの心持ちが伝わってくる。彼女は昨年多くの時間を米国で過ごしたという。ニューヨーク近代美術館で開催された「Artist’s Choice: Spirit Movers」にてキュレーションを手がけたことが契機になったのだろうか。ワシントン州にあるハワード大学の歴史が琴線に触れたようだ。「ハワード大学での経験は、想像力豊かな出会いであり、輝かしい系譜を讃えるものです。特に1990年代の卒業アルバムには、ヒップホップのパフォーマンス、詩人の朗読、キャンパスの緑地での国際的な集合などの描写が響き渡ります」とコレクションノートには記されている。米国のラッパー、ヤシン・ベイのライブパフォーマンスによって学会のような雰囲気のショー会場にヒップホップのリズムが加わることで、複数の領域や世代に跨って知識人や芸術家を交差させ、文化的な関係性を育む根底が見え隠れする。ファッションデザイナーとして、この複雑な思考と魔法のような融合は、研究領域だけでは昇華することができないリアリティーを帯びた洋服として蒸留される。


Wales Bonner AW2024-25
アフロアトランティック文化を中心に西洋の文化、遺産、文脈を溶け合わせ、ここ数年で持ち得た軽快さという含蓄のある下地をそのままに、2022年からウィーン応用芸術大学にて開始した「批評と希望の間」という研究プロジェクトの主任研究者として、グレースは、ポリリズム(異なるリズムが同時に奏でられ、クロスすること)を追跡することでアーカイブ実践や黒人文化表現にとって、それがどのように機能するかを再考する。そして、それは発掘された資料の流動的な記録をデジタルプラットフォーム上で確立させ、アーカイブを人々が没入できる別の空間、時間、歴史、領域への入り口として考えることを目的としている。それは、過去を持って過去から遠ざかろうという行為とも捉えることができるのではないか。
サヴィルロウにある伝説的なビスポークテーラー「アンダーソン&シェパード」との継続的なパートナーシップによるシルクトリムのタキシード、カシミアのダブルブレストコートやヴィンテージのキルトのパーカやブルゾン、実用的なデニムや端麗なドレスシャツ、インドの職人の手仕事による鉤針編みの鏡の刺繍が施されたスーツ。そのどれもがアカデミックなワードローブとして組み合わされており、そこにアスレチックなシルエット、コーデュロイのブルゾン、サテンのベースボールジャージといったハワード大学のスポーツヘリテージを反映させている。「ティンバーランド」との協業によるシルバー装飾のワークブーツや「アディダス オリジナルス」との協業では、スーパースターシリーズを引用したセットアップやスニーカー、そしてスリーストライプスのトレフォイルロゴのバッグなど、抜け眼はない。こうした交差は、ハワード大学での経験、ウイーンでの自発的な研究、そして洋服に宿したそレラすべてを頌歌するかのように刻むビートは鼓動をさらに高める。


Wales Bonner AW2024-25
ファッションは随分と現実的になったといわれる。より極端な意見として、過度に市場に依存しているとも。身近に感じるデザインというのとは少しニュアンスが異なるが、大切に従おうとするかの如く尊ぶ傾向が確かにあるのかもしれない。コレクションノートには、1920年にハワード大学を卒業したゾラ・ニール・ハーストンの一説としてこう記されている。「西洋の荒々しく、端正なフレーズは、官能的な太陽の子にとってはあまりにもむき出しに見えるので、装飾品になっているのです。 それはジュエリーを身に着けたり、彫刻を作ったりするのと同じ衝動、つまり装飾をしたいという衝動から生まれます」。この節を刻んだグレースの真意はわからないが、装うこと以上の意味があると、言外に匂わせているのかもしれない。グレースの探究という一種のリアリティーは歴としたファッションの物差しであり、「ウェールズ ボナー」の提言には小気味好さがある。エキセントリックな所作こそ、グレースの探究の範疇ともいえる。だから彼女が作った服には、不思議な求心力を秘めている。もしかすると着る側の個性をも剥奪しかねない巧妙な均衡を晒すデザインは、ファッションの時流を顧みないグレース・ウェールズ・ボナーの流儀だろう。