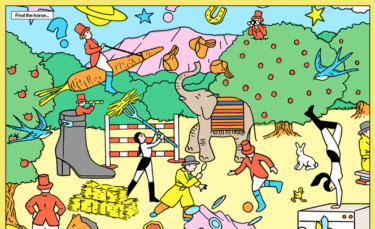- 1 自分が帽子を被っていると、帽子を被っている、という意識が明確にある。それは当然だ、と感じる人もいるかと思うが、洋服を着ていて、洋服を着ているという明確な意識を持って生活しているか、といわれると疑問に思う。それに対して、帽子は帽子を意識しながら被っている。だが「キジマ タカユキ」の帽子は、不思議と帽子を被っているという意識が薄れる。それほど身体に馴染んで一体となっているといっても過言でない。デザイナー、木島隆幸は帽子デザイナーとして約30年の経歴がある。それ故か、木島の言葉には、自身が作った帽子のように、こちらの意識と馴染む。自身の名を冠したブランド創業10年を迎えた今、自身の歩みを語ってもらった
- 2 帽子と出会う以前。意外なスタイルとロンドンで受けた衝撃
- 3 転機となった2つの出会い
- 4 日本人と帽子。そして、自らが思う職人として向かう次なる先
自分が帽子を被っていると、帽子を被っている、という意識が明確にある。それは当然だ、と感じる人もいるかと思うが、洋服を着ていて、洋服を着ているという明確な意識を持って生活しているか、といわれると疑問に思う。それに対して、帽子は帽子を意識しながら被っている。だが「キジマ タカユキ」の帽子は、不思議と帽子を被っているという意識が薄れる。それほど身体に馴染んで一体となっているといっても過言でない。デザイナー、木島隆幸は帽子デザイナーとして約30年の経歴がある。それ故か、木島の言葉には、自身が作った帽子のように、こちらの意識と馴染む。自身の名を冠したブランド創業10年を迎えた今、自身の歩みを語ってもらった

帽子と出会う以前。意外なスタイルとロンドンで受けた衝撃
――幼い頃の帽子やファッションに纏わる挿話は?
子供の頃に帽子を被っていた記憶があまりありません。今も尚そうで、滅多に帽子を被らない。そもそも機会も少なかったように思います。ファッションに関しては小学校5,6年生の時、洋品店に行って、ベルボトムのジーンズにサファリのジャケットを選んで、親に買ってもらった記憶があります。中学の時には親戚のお兄さんの影響もあって、ネクタイが恰好好く思い、グリーンのシャツに金色のネクタイを組み合わせたり。中学3年くらいになるとワインレッドのベルベッドパンツを履いていました。特に参考にした人もいなく、直感で選んでいたと思います。
――帽子作りに携わるキッカケは?
高校を卒業しても特に定職に就くわけではなかったのですが、20歳くらいの時に海外に行ってみたいなと思い始めて、アルバイトをしながら貯金して、半年ほどロンドンに行きました。それが初めての海外で、1988年のことです。ファッションでは、少し前にマルタン・マルジェラが飛躍し、アントワープシックスがパリで活躍していた頃です。ロンドンではヴィヴィアン・ウエストウッドがパリに行く前。ただ、デザイナーズブランドから何かを学んだのではなく、最も勉強になったのは街行く人たちのスタイルです。日本はバイブルがあって、型に嵌ったスタイルが多くありますが、ロンドンでは友人がスーツにアメリカンな作業用のワークブーツを合わせていて、衝撃を受けました。この自由な感覚に高揚したのは確かです。それと、実はロンドンに行く前に将来のことを考えていた時に、ファッションに携わりたいなとは思っていたのです。ただ、自らのファッションの遍歴を振り返ると、あまりにも優柔不断だと感じていました。古着、ロンドンファッション、ジャージなどのラフな出で立ちからスーツスタイルまで。そんな右往左往する人間が洋服のデザインはできないだろうなと。そこで、小物が浮かびました。特に靴が好きだったので、最初は靴を作る学校を調べてみたのですが、学費が高くて断念しました。そんな時に「アンアン」を読んでいた友人が平田暁夫教室の広告を見つけてくれて、年間の授業料も安かったので、帰国後に通うことを頭の片隅に入れておいたのです。ロンドンに行ったことでそれが決意に変わりました。

転機となった2つの出会い
――平田暁夫(1960年代に渡仏してオートモードの巨匠ジャン・バルテ氏に師事。オートモードの技術を日本に持ち帰り、皇室などの帽子を製作していた)との出会いは、自身のキャリアの中で欠かすことができないと思うが?
ロンドンから帰国してすぐに、平田先生の教室に通いました。ただ、平田先生が直接指導してくれるわけではなく、担当の先生が帽子作りを教えてくれました。学校ではなく、教室なので週一回の授業。他の日はアルバイトに明け暮れていました。日本経済はバブル期。内装業をしていて忙しくて課題もろくに出来ていなかったので、決して真面目な生徒とはいえませんでしたね。一年で修了のコースを終えて、上級者コースに行くかどうかを教室の先生に相談したところ、成績不振のため昇格できるわけもなく。ただ、平田先生のアトリエで人材募集をしているかどうか聞きに行ってくれたのです。平田先生の教室の上の階がアトリエだったので、すぐに聞いてきてくれて、運良く募集していたため、アトリエで働くことになりました。僕が25歳の時で、そこからは怒涛の日々でした。平田先生のアトリエはオートクチュールのアトリエなので、流れ作業ではなく、一つ一つ工程も違うため、とりあえず手を動かすことを徹底していわれました。何か教えを講じるのではなく、見て学ぶ。「コムデギャルソン」「ヨウジヤマモト」を始め、あらゆるブランドから依頼があったため、それぞれ異なる素材、アプローチで柔軟性と応用力を鍛えることができました。今でもその力は活きていると思います。平田先生との逸話?実は、ほとんど会話したことがないのです。途中経過を見せに行き、「ここは違うから直して」といった会話程度。厳しいとも感じたことはなく、雲の上の存在です。僕もまだ帽子作りを志して間もない頃だったので、先生の思い描く表現に追いつけなかったと思います。ある日、先生に「日本語がわからないならフランス語で話すか?」といられる始末です(笑)。先生が何を求めているのか、を解釈することに必死で、頭の中が真っ白でした。30歳までアトリエで働いていたので、計5年。とても大事な時期を過ごすことができたと思います。最も痛感したことは、帽子を完成させるまでに無数のアプローチがあるということ。ものづくりにおいて、画一的な手法など存在しない、ということです。一つに集約してしまうと、新しさは生まれない。それはウチのアトリでも伝承していて、スタッフに一から教えることはありません。もちろん基本は伝えますが、僕はこうやるけれど、という前提があります。自分のアプローチを見つけてほしいという意味を込めて。

――独立後、「クール」を創業。「シンプルな装いの中にも存在感のある、トータルコーディネートで生きる帽子」というコンセプトは現在のブランドにも通じるが、その真意は?
作り手である以上、自分でやりたいと思う野心はあったのだと思います。1994年12月にアトリエを退職した後、1995年2月にパリへ視察しに行き、同年の春頃に事務所を構えました。前身の「クール」は、フランス語でハートの意があることと、パッと見で発音できないような曖昧で不透明な字面が良かった。立ち上げ当初に作っていた帽子は、平田先生の創意を継承しているかのような、クチュールライクで装飾的な帽子でした。というのも、平田先生のアトリエにいた5年の間は籠り切りだったため、ファッション業界のことが全くわからなくなってしまいました。そのため、独立した後もそのイメージのまま作ってしまったのです。セールスもそのための段取りもわからない。そこで唯一知り合いだった栗野(宏文)さん(現・ユナイテッドアローズ 上級顧問クリエーティブディレクション担当)を頼りました。栗野さんとは、まだ平田先生のアトリエで働いている頃に知り合いました。通りがかったユナイテッドアローズ渋谷の一号店が気になって入ってみると、2階のメンズフロアには上品でクラシカルなスーツで囲われていながら、入って右手前には「クロムハーツ」のライダースもあって。僕はロンドンファッションに身を包んでいたのですが、栗野さんはネクタイにポケットチーフをして接客されていて。それに影響を受けて、栗野さんにスーツを作りたいです、とお願いしたこともありました。それで気になったのか、栗野さんが話しかけてくれて。「帽子を作っているんだね」と顔見知りになりました。そういった経緯があったので、ブランドを始めたこと、そしてその時に壁にぶつかっていることを栗野さんに相談しに行きました。当時、本社があった原宿のビルの最上階のカフェ。そこでサンプルを作って展示会をやること、オーダーを取って展開することを教えてもらいました。その後、サンプルを見に来て下さって。一言目で「この帽子が素晴らしいことはわかる。でも、これを被るシチュエーションが浮かばない」と言われました。血の気の引くような衝撃を受けましたね。同時に、そうだよな…と。目から鱗が落ちるとはこのことで、当時は良いモノを作れば、売れるという画一的な考えがあって、それを崩してくれたのが栗野さんでした。ブランドのアイデンティティーの根底はその逸話があります。日常着において、帽子は無くても成立する。帽子という存在は、帽子がないよりもあったほうが恰好好くなるべき。ファッションを楽しむ人たちにどのように寄り添うことができるか、がコンセプトになります。

日本人と帽子。そして、自らが思う職人として向かう次なる先
――日本人と帽子の親和性についてどのように感じているか?
個人的な視座ですが、日本人は自身のスタイルに合わせて帽子の被るのが上手だと思います。30年前は帽子ブランド自体が珍しく、ファッションで取り入れることがポピュラーではなかった。「キジマ タカユキ」はスタイリストの祐真(朋樹)さんが「ポパイ」で使ってくれたり、僕だけの力だけではなく、帽子を作るブランドや作家たち、それをサポートする関係者の地道な努力によって、浸透したと思います。それに洋服の歴史は浅く、先入観がないので、自由な被り方が可能なのだと思います。他方、西欧では伝統的なスタイルやシチュエーションによる帽子の使い分けがいまだに残っている印象があります。頭のサイズに関していうと、さほど変わらない。形は少し異なるかもしれません。比較的に東洋人は少しだけ丸い。好まれる帽子の形は…どうでしょう。海外ではクラシカルな型が好まれやすく、日本人はカジュアルな帽子をスタイルに取り入れるのが上手。帽子の発祥は、世界最古といわれる「ジェームズ・ロック」が生まれたイギリスといわれていますが、ファッションの都であるパリほど根付いていないと思います。逆にいうと、帽子はその地域毎にフラットに根付いているのではないでしょうか。
――自身にとって、職人とは?
これに関しては大きな基点があります。僕は滅多に帽子を被らないことを公言していますが、被ってもらうのは大好きです。だからこそ、帽子を被る上でのストレスは、十二分に理解しています。独立当初、帽子は洗えないため夏に白い帽子を被ることができない、ということに対して疑問に思いました。そのため、洗えるように縫製をして自分でサンプルを作りました。けれど、量産の方法がわからなかった。関東中の職人さんの工房を自ら一軒ずつ出向いたのですが、頑なに受け入れてもらえない。平田先生のアトリエで「これはできない、やらない」といわれたことは一度もありません。僕にとっての職人は、伝統を継承するだけではなく、時代に合わせて更新させていく人たちのことだと思っています。そういう意味で、自分自身をデザイナーではなく、職人だと自負しています。
――次の10年に向けて、どのようなビジョンを掲げているか?
より一層、国内外といった境界線がなくなっていくと思っています。今も徐々に増えていますが、海外ブランドとのコラボレーションも積極的にやりたい。日本のファッションブランドに対して、「キジマ タカユキ」のマインドの理解は深まってきていますが、海外のデザイナーはまだまだ。コラボレーションの依頼が来た時に、どのように作って良いかわからないと言われることもありますが、それで良いのです。帽子に対する知識は必要ないので、まずは声をかけて欲しいなと思っています。