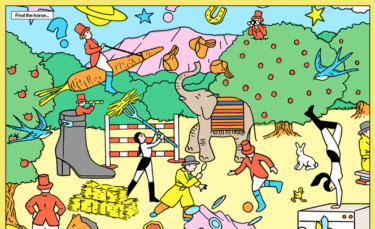FEATURE|The possibilities of viewing the works depicted in the solo exhibition “Contours of the Unseen” – Artist Towa Takaya

鎌倉画廊にて、アーティスト・高屋永遠の個展「真空の輪郭」が12月25日まで開催中である。高屋は物質のふるまいを通して人間の知覚の根源に向き合い、内省を経て存在が朧げになる自らの空間や認識の根源を探究し、時間の不完全性、不可逆性、身体感覚の行方を円観的に広がる表現として昇華させている。本展「真空の輪郭」では、「青のシリーズ」の発展である「罔象シリーズ」をはじめ、能登・珠洲の土や砂などのローカルな素材を用いた「大地シリーズ」、そして自然のダイナミズムを極小の視点から見つめる「苔シリーズ」など、多岐にわたる作品群を一堂に展示することで、連鎖を経て、認識の拡張とその過程に何が起こっているのか、そして、日常では見過ごされる不確かさを実験的に推察する。本展のために寄せられた高屋のステートメントにはこう記されている。
「真空の輪郭」は、空無ではなく関係の縁を隠喩します。私は色を単なる情報としてではなく、展示環境や鑑賞者に応答するような生命のようなものとして扱いながら制作をしています。自然環境から採取した土・植物・化粧原料・金属などから自作した色材を光学素子として捉え、反射・屈折・散乱といった素材本来の自在なあり方を探究しています。
鑑賞者の眼差しの変化と光環境に応じて、絵画空間は常に異なった様へと立ち上がり、実在光のもとで像は現象へと転じます。作品は、環境と身体が共鳴することで感じることのできる現象的なものであり、開かれていく「経験」です。
本展では、質感の位相、視差の臨界角、各絵画層間の反射など素材の特性の可視化を試みながら、輪郭=境界のゆらぎとして考察していきます。
―高屋永遠
絵画を描くことを超えて、物質の変化を通した人間の存在と事象、現象の関係性を探る行為には、作者と作品の関係性も深く関わってくる。このインタビューはその関係性を探った過程と経過の一部に過ぎない。

―本展の主題の根底には、作品そのものに素材の実験性や芸術の媒介性を思索するよりも、概念的な思索に傾いているが、本展の起点は?
高屋永遠(以下、高屋): これまでは素材の実験性や光に対するふるまいを探ってきましたが、今回は「人間がものを見る」とはどういうことか、そこを突き詰める認識論的な問いが起点になっています。
その過程で、私たちは万能に、あらゆる事象を決定付けながら全てに行き届く手法でしか世界を認識していないのかもしれない、という根源的な認識論の限界みたいなものを感じながら素材の実験に向き合ってきました。なので、今回は手法や手段ではなく、私自身が向き合ってきた“認識の不完全性”そのものを展示の中心に置いています。
その不完全性こそ明日とか明後日という長い時間の尺度を自分たち自身に許容して世界と関わっていくことだと思います。
こういうものだから…と放棄してしまうことを断定できないからこそ、ある意味で可能性を広がっていくことを作品の中で示唆しています。有限であり、しかもその有限性が確定していない…例えば、今は青く見えるものだったとしても明日は青に見えていないかもしれない。夕日も毎日繰り返されるけれど、同じ瞬間は二度と起こらない。その不可逆性に触れることは、自分の生命の一回性を思い出すことにつながります。その感覚を、本展で静かに示したいと思いました。
―それは詰まる所、時代や社会に対する言語外の言及としても窺えるが、その契機となる出来事などがあったのか?
高屋: 災害や環境問題、あるいは戦争やパンデミック然り、2020年代以降に人類が直面せざるを得ない問題が次々に起きていますが、そのような具体的な出来事が契機となっているわけではありません。その総体は各所に点在していて、皆が違う場所にいて、全てを同じように体感することはできません。具体的な問題よりも人間であること、潜在する認識そのものに関心を引き戻したいという思いです。逆説的ではありますが、オンライン上に情報は溢れているけれど、全てが確定してしまう危うさ…ポストトゥルース時代と呼称されることもありますが、その情報が真か偽か、ということは明確に判別できない。画面を見ているだけではわからない時に、どうすれば本当の意味で世界と「触れ合える」のか。
つまり、見るという行為は視覚情報を流布しているのではなくて、身体を伴って作品や空間と関わることだと改めて感じさせられました。だから見る角度によって見え方が変わるなど、この空間に来ないと体感できないような味わい方、奥行きの変化というものに関心が向きました。作品の見え方が角度で変わるように、身体を伴って経験することは、確かに世界と関わる行為になります。生きていることの確からしさを美術という言語、形式の中で体現できるのか、という問いに向き合った感覚です。それは、インビジブルな情報ではなくビジブルで触ることのできる物質の変容に人間の身体が反応することを美術制作の主題に添えることは可能なのか、という試作でもあります。

―美術を通して人間の根源に触れる行為は、作者としてある種の恐れがあって然るべきだと思うが?
高屋: もちろん、個人的な他者や時代との関わり方にもよると思いますが、普遍的な認識論への関心は、特定の個人というより「私たち全体」の課題であると感じています。
ファンダメンタル的且つこの時点でこの主題を扱うことに対して、恐れがないというよりも、必然として引き受けている感覚です。もっと社会政治的なことに触れていたらそうなることもあると思いますが、この主題はあまりにも普遍的で、ありふれていたはずの主題です。例えば、言葉をしっかりと取得していない幼少期であっても、手探りに自分から見た世界を認識しようとしています。だからこそ、恐れというより、光や風景の流動性と向き合うことは自然な帰結でした。いままでも光というものを扱ってきたので、風景の中の流動性であったり、光の中で生きるもの、それを生かすものの根源は果たして何だろう、と改めて問い直したかった。そういう意味では、この展示はひとつの新しい始まりの地点であり、これまでの探究を一度立体化して見つめ直す総括のような位置づけでもあります。
―鑑賞者と作品の関係性を追うことも作家としてのアイデンティティーのように感じるが、そこに向き合う契機とは?
高屋: 英国留学時のラストイヤーでは、ジェンダーステディー、ジェンダーポリティクスについて掘り下げていたのですが、その過程で「言語の構造が世界の見え方を固定する」という限界を実感しました。
女性だからとか男性だからとラベリングしてしまった瞬間に今までそれでよかったものが決定付けられてしまう。言語は、その判断する行為自体を兼ね備えている。それと同時にビジュアライズする、例えばこれは赤いリンゴです、と書き記した時点で赤いリンゴになって、それ以上の余白には広がりません。私の制作を振り返ると、身体を使って記号的な図像を描いていた「Proposition」という創作初期のシリーズがあるのですが、その時に色に意味を持たせること、形が意味を持ってしまうことのある種のネガティブな側面に対峙しました。それがあって、形が溶けていくような、それでいて天も地も固定されない奥行きや揺らぎとして広がっていく生命の感覚を書き始めたのが「青」シリーズを描いていた2017年頃です。もちろん人間の認識は、見るところを固定しないとそもそも日常生活に支障が出るような混乱をきたすと思うのですが、だからこそ美術という鑑賞体験を通して、認識の緩みや余白であったり、言葉にならないけれど展示や作品を通してオーディエンスと何かを体感することの信頼を共有したかったのです。
私の作品と展示の特徴として主客の区別がほとんどありません。鑑賞者と共有する“場”として成立しており、それを誰かが所有する構造にはなっていません。
そのため、作為性は自然と削ぎ落とされ、素材・光・空間・身体が互いに応答し合う「共有地」として作品が立ち上がります。作者のメッセージを読み解く鑑賞者という力関係は働かず、みんなで展示という一つの場を経験し、それぞれの認識をシェアしていくようなものです。

―「見る(観察する)」を定着する(作品に転換する、日常化させる、展示する)までのプロセスについて
高屋: 展示の主題だけではなく、作品タイトルも断定的にしていません。場のように開かれたタイトルなので、あの時はこう見えて、こう感じられたからこの作品がいいと思ったとします。でも、2年後、5年後と時が経っても創作活動は続けていて、鑑賞者も見てくださっているとすると、時間軸が延長されて、最初にその人が見た作品が更新されていく余地があった方が良い。大量生産されない美術作品だからこそ、見るという行為に耐え得る何度も解釈し直せる、鑑賞し直せるような作品の経験を作り出したい。
例えば「罔象」「開闢」シリーズもこれは5連作として当初発表されているひとつの作品ですが、一度の見方で固定されず、場所や季節、光によって姿が変わる現象として設計しています。今日はその題名と導く光の震えに着目していても、また別の日には別の層の構造に目が向いたり、何度も読み直しているうちに、見ている側が自在に総体を組み直すことができる。作者である私も再解釈できたりできるものとして考えています。作品が多層的に作られているので、その現象に身を委ね、体験してもらいたいのです。作者である私が一方的に意味を付与するなど、そういう形式にならないように心掛けています。だからこそ、一作を描くのに時間が必要になっていく…即時的で一過性の判断や感情で決め切らない。何度も内省していくプロセスを経て、創作することと距離ができ始めて初めて、こういうものだったのかもしれないと作品を手放すことができる。なので、素材の実験にかけている時間も長いですが、だからといって具体的な数値を計測しているわけでもなく、どちらかというと私の内面の中でどうしたら物質を通して翻訳できるか、試行錯誤している時間が長いのかもしれません。それが瞬時にプロセスされない、昇華されないからこそ、時間がかかってしまいます。私と作品の関わりも一回性があります。その中で、なるべく光の揺らぎが積層していくような構造を持つので、あらゆる空間や文脈の中でも読み直せるものとして、作品それ自体が自立して立ち上がるまで、静かに見届けるような感覚です。創作を通していくと私自身もこの光とかこの感覚に対して、どのような体験をしたか、自分自身も確認できる場になる。それは次の創作に繋がりますし、両方が自立しています。そのプロセスを通して、日々新たに毎日世界と物質と出会い直し続けられる。

―「真空の輪郭」という主題は「罔象」、その根源となった「青」や「大地」「苔」という連作とどのように呼応しているか?
高屋: 「青」や「罔象」シリーズは認識の領域性、見える・見えない、感じる・感じないとか、人間が世界をどのように見るかという揺らぎを問いかけています。
また、「大地」シリーズとかは土地が抱える記憶という不可逆性が物質として堆積していっているという視点から「時間の累積」です。それに対して「苔」は、湿っている感じとか微細に揺れているとか育っている感じとか接触感覚を促進させる主題としての生き物の気配を扱っているので、つまり身体感覚と生命の領域です。そして、これらがすべて交差する地点が「真空の輪郭」です。
各シリーズの背景にある概念的な階層を見せつつ、それぞれのシリーズで試みたことが相互に交差するような螺旋状の空間にしたかった。観る人も私の内面構造を体感できるようにフィジカルに立体化されていると思います。12月18日から最後の1週間では、CO2を活用して生成される次世代ポリマー素材を用いた新作「Morphology of Breath 呼吸の形態学」も展示します。これは気候変動に向けた新素材を手がかりに、呼吸の循環から生成されるCO2が新たな物質に転換し、光、身体、環境が交差する“現象”として立ち上がる過程を探究した作品です。 現象学的な知覚の揺らぎを通して、世界との関係性を新たに問い直しているので、既に展示されているシリーズとも呼応しています。

―鎌倉画廊で展示する意味や今後の可能性について。また、鎌倉という土地をどのように捉えていて、そこで1ヶ月以上も展示するという「経過」に関して、どのように考えているか?
高屋: 秋から冬への光の変化は、作品の見え方そのものを変えていきます。つまり今回の展示は、一ヶ月をかけた“公開実験”のようなものです。
もの派が探求した「物質と場」の問題系を受け取りつつ、私はそこに身体感覚や触覚的な経験を重ねながら、人間の認識が常に不完全であること、そして時間とどのように接触しているのかという問いを扱っています。
情報が即時に確定され、世界が「分かったもの」として消費されやすい現代において、認識の不確かさや時間の不可逆性をあらためて引き受け直すことは、素材や現象と向き合う別の態度をつくることでもあると考えています。
私の制作は、パール材や二酸化炭素活用素材などの技術的な試みや物質性の拡張を通して、人間が世界とどのように関わり続けられるのかという根源的な問いを、今の時代において更新し続ける試みです。
会期に関しては、例えば視覚とか触感を刺激された鑑賞者も、なぜこの並びなのだろうとか、なぜ「青」「罔象」のシリーズがあり、「苔」があり、「大地」のシリーズ、とこの3つの連鎖があるのだろうとか、ふと立ち止まって理由というか奥にある思索を感じ取った時に、別の見方で見えるような。時間をかけて見たとしてもまだ奥がある、と見続けられるように、と考えて設計しました。
今回は新作発表ではなく、これまでの核を読み直す展示です。作品を「見せる」のではなく、「読む」ように身体的に関わる構造を意図的に設計しました。濃度・純度・深度を徹底的に考えました。

―作者と作品の関係について。自らの媒介を以って媒介を、作品を以って作品を更新していく行為は文化研究者、山本浩貴氏がいう作品の「円環」つまり、循環的な行為ともいえるが、作者としてはどのように感じているか?
高屋: 山本さんに仰っていただいた「円環」に関して共感する一方で、私の取り組み各々は絶妙にズレが生じながらも螺旋状に発展しています。
非対称の生成といいますか、同じことは繰り返されず、少しずつの差を生成していく。作品が生まれたことで別の視点が立ち上がっていく。それを積み重ねていくと、自分の無意識のバイアスとか眼差しの限界とか、見るだけではなく触れてみたいと思うことも含めてですが、次の創作の条件を作り出していきます。素材、作品、認識、再生成を往来すること、同じ場所には戻らずに異層に向かう運動と捉えていて。現代美術において、素材とか現象を扱う実践は多くあると思うのですが、作者の認識の変化、揺らぎそのものが作品、創作の成立条件として書き換わり続けるのは稀だと思うので、自分で自分の作品を通して実験しています。私というよりも他者が触れていくことで認識はどのように変わっていくのだろうとか、その実験を続けている感覚です。だからあまり主客がないのだと思います。そこに言語で考えるという行為を挟まないので…感覚的であり、触覚を喚起する何かであり、言語的な組み立てを経由しません。純粋に光の向きとか振る舞いに向かって探っていく。深く光を探っていくと、感覚が溶けていくような、そういう感覚になっていく。色や造形も二次情報になっていって、触れていることそのものが作品体験へと変換されることで、認識の根源とも言えるところまで感覚が至る。
今回の展示では、その全体的な「編み直し」を初めて大規模に行いました。作品が自立し、時間を越え、鑑賞者とともに更新されていく。その過程を共有できる展示になったと思います。色や形による説明ではなく、体感として、作品を感じ何かを受け取ってもらえたらと願っています。