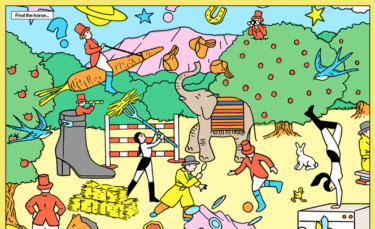FEATURE|山岸慎平(BED J.W. FORD)×川上洋平([Alexandros])創作の微細な本質を語り合う|前篇

本誌「QUOTATION FASHION ISSUE vol.38」にて「ベッドフォード」と山岸慎平の創作の背景を辿る「Close-up」という企画を設けた。そこでは2023年2月に発表した2023-24年秋冬コレクションから始まり、2023年6月に単独では初となるパリメンズファッションウイークでのランウェイショー、8月には初の旗艦店を東京、外苑前にオープンまでの山岸慎平の約半年間に迫っている。主題は「虚像と実像」。
本企画を通して、その輪郭を明確に象ることができたかは定かではない。寧ろそれらを曖昧なままに、ピン留めしている状態が、山岸のありのままの姿かもしれない。核心に触れるのは我々の仕事だけではなく、何か引き金が必要ではないだろうか。
そこで真っ先に浮かんだのがこの度のトリガー、川上洋平。[Alexandros]のボーカリストとして活動しながらラジオDJや俳優など、あらゆる表現形態で自らを解放する川上と山岸は、表現者としての関係性だけではなく、私的な交流もある。言葉という創作の微粒子を交わすことで、また新たな一面を覗かせる。この二人が表舞台で対話を交わすのは初めてのことだという。百聞は一見に如かず、二人の言葉を覗いてみようと思う。
ステージで自らを解放する川上、羨望の眼差しで見つめる山岸
――どのように出会い、どのような印象を抱いたか?
川上洋平(以下、川上): もちろん会う前から「ベッドフォード」のことも(山岸)慎平君のことも知っていました。ある時、慎平君が(庄村)聡泰君(元[Alexandros]ドラマー)と交流があって、ライブを見に来てくれて。ライブ後の楽屋挨拶で初めて挨拶しました。
山岸慎平(以下、山岸): そうだったね。僕も洋平君のことはもちろん、バンドとしては「Waitress, Waitress!」という楽曲のMVを見て、面白いアイデアを表現する印象がありました。ライブを拝見できて良かったと思っていた最中、当時の「メゾン ミハラヤスヒロ」の陵本(望援)社長が間に入ってくれて、「ミハラ」の事務所で時間をかけて言葉を交わして。
川上: それが5年くらい前かな。僕にとってのファッションは、私服がメーンではなく、ステージ上での装いが軸となっています。日常着と衣装という2つの世界における捉え方があって。ただ僕の中で音楽という表現は、プライベートとステージを分けていない。ミュージシャンという自覚をもって、普段から所謂オンステージのように良い服を纏いたいと思っています。そういったステージではありのままの自分でいたいと思っていた時期に慎平君と出会ったんだよね。僕にとってステージは自らを解放できる場所。オンではなく、寧ろオフ。多分、普段の自分の方がピシッとしているかも(笑)。
山岸: そうだね。ファッションと音楽の近さは頻繁に語られるけれど、僕は個人的に思うことがあって。全員ではないにしろ、ファッションデザイナーはミュージシャンに片思いしている感覚があると思っている。羨望の眼差しで見ているのではないかなと。世代的にもミュージシャンは憧れの存在。自分の身一つで世界を変えることができる。そして、そこには明確なストーリーがある。だから、わざわざ語ることでもない気がしていて。洋平君がいっていた衣装についても、川上洋平にはずっと川上洋平でいて欲しい。誤差のない姿。それは、僕が目指している世界でもある。

――お互いのランウェイショーやライブに対してはどのように感じたか?
川上: 代官山のリストランテASOで発表した2023-24年秋冬コレクションのランウェイショーで初めて「ベッドフォード」のショーを拝見しました。他のブランドのショーも見たことがあったのですが、まず場所のセレクトが素晴らしかった。何か荘厳な催しに来たのか、と思うほどの独特な空気感に圧倒されました。洋服に関してはいうまでもなく、ショーを観ながらどれを買おうと選んでいました(笑)。相変わらず恰好好い世界を作る人だなと。ランウェイショーの芸術性についてですが、例えば音楽一つとっても、僕の場合は音楽を作っているからか、音楽というジャンルの中で掘り下げるようなことはしません。むしろデザイナーのビジュアライズの一環の中での掘り下げ方に驚かされます。知識の深さと自らが生み出す世界観との整合性。まだ浸透していない新人ミュージシャンに目を向けていたり、アンテナの貼り方が凄まじいなと思います。そのため、ブランドのショーでどのような音を使っていたかを頻繁にチェックしています。
山岸: [Alexandros]のライブを観た率直な感想は…俺にできない。それに尽きます。自分たちがやっていることに矜恃がありますが、あの動員数の観客に見てもらい、しかもその瞬間にしか味わえないエネルギーを放出する。ステージ上がる前は緊張するのかなとか、そこに至るまでのマインドセットとか、それは洋平君にしかわからないことで、周囲に共有することはできない。自分も精神的に共有できない部分があるけれど、大きなスケールで背負っている姿には、本当に痺れます。ライブが良かったとか、そういう単純な話ではなく、洋平君の創作に対する意識とか。それを解放する時の緊張感は特別だなと思う。
川上: 確かに緊張感はあるけれど、意識しているところと無意識なことがある。怖いとか思うことはないのに、何故かライブの前日と後日は寝ることができなかったり。
山岸: すごくわかる(笑)。ショーの場合は大体一発勝負で、多くて2部制に招待客を分けることもあるけれど、音楽の場合ツアーがあるからね。緊張感が一定の期間続きそう。
川上: 全国ツアーや海外ツアーは、確かに緊張感が続くかな。でも、それはいいことだと思っているよ。その期間にしかない自分のマインドがあって、その時にしか作ることができない曲調もある。制作期間に作る曲とツアー中に作る曲では大きく異なる。でも、その時の気分に乗じることを楽しんでいるかもしれない。
山岸: その時の気分に乗じることは、とても大切にしている。6月のパリメンズファッションウイークでのショーの時も、単独としては初めてのパリでのショーに向かう、その過程では高揚感と恐怖心が行き来していて。楽しめたかどうかは覚えていないけれど、その時の自分の気分に乗じることは大事にしていたと思う。
川上: 僕から見ていると、ファッションデザイナーは年中ある一定の緊張感があると思っているけれど、実際はどうなの?僕らの場合、制作期間を設けたり、ライブ期間にしたり、自分たちである程度はコントロールできるけれど、ファッションの世界には、年2回新作を発表するという特殊なサイクルがあるよね。
山岸: パリで発表しながら日本でも活動するという現行のステージから降りて、自分たちの独自のルーティンで活動していくことも不可能ではない。ただ、もう今を頑張りたいかな。もっと月日が経ったらわからないけれど、今はハイペースがマイペースになっている。年中、緊張感があるか…確かにそれに近い感覚はあるかもしれない。いざコレクションを作り始める瞬間の感覚は毎回異なる。ただ大きく分けると、すぐに創作に向かえる場合と疲弊し切ってなかなか進まない場合がある。その時の世界観の取っ掛かりが見えてきたらかなりペースは上がるし、緊張度も高まる。ただそれはあくまでも取っ掛かりであって、そこから練り始める。そうなってからはあまり人に会わないし、決まったものしか食べない。すべてが面倒になっていくんだよね。

BED j.w. FORD SS2024 Photo: Genki Nishikawa

[Alexandros] But wait. Arena? 2022 supported by Panasonic at Yoyogi National Stadium First Gymnasium Photo: Yuki Kawamoto
創作の母体である集合を個として捉え、主語を共鳴する
――現代においてグループの総合力は重要なファクターになっているが、チーム作りについてどのように考えているか?
川上: 僕は音楽を始めた瞬間からグループでした。だから、僕にとって集合は個でもあります。僕がフロントマンだからといって、引っ張っていく、という気概もない。メンバーがいるから自分らしくいることができる。周囲のスタッフのことは、かなり考えます。照明や演出だけではなく、グッズ制作も作品の一つだと思っているので、自分たちの思いを伝えます。もちろんソロプロジェクトとかも興味がないわけではないけれど、バンドは創作の母体なので、今はバンドに集中しています。
山岸: 洋平君にこの質問をしたことがありました。「ソロでやりたいと考えたことはないの?」と。当時の僕にはベッドフォード以外で自分を見てみたいという気持ちがあったのです。洋平君でいう [Alexandros]ではなく、川上洋平として向き合ってみたいと思わないのかなと。ただ、洋平君の答えは「いつかね」の一言でした。タイミングではないということなのかなと僕は解釈して、それを見極めるのも作り手としてあるべきアティチュードだと思います。洋平君と話したことと自分の頭の片隅にあった思いを重ねて、今ではないというフレーズが妙に腑に落ちた覚えがあります。そこからは改めて「ベッドフォード」をどのように育むか、ということだけに集中できた。だからこそ、今の環境があると思っています。そうなってからのチーム編成は、個性もあって非常に面白い。まず全員の主語が「ベッドフォード」になっています。「僕は」ではなく、「ベッドフォードは」です。主語が共鳴できているチームは強いと思います。それと同時に、パリで挫折したとしてもまた一からやり直せば良いと腹を括ることができている。それは洋平君がいう「集合が個になっている」状態に近しいのかな。それと、僕らがフロントマンであることは単なる偶然で、メンバーが担いてくれる神輿の上で恰好好くいようとしているだけです。