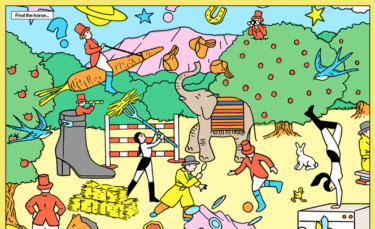VEIN|前作で示した態度はそのままに手垢と汗が迸る2024-25年秋冬。ありのままをスタイルに変容させる榎本光希のロマンチシズム

VEIN FW2024-25
「これまでで最も私的なコレクション」と榎本光希本人も発していた2024年春夏。自我と向き合うこと、それは自身が手掛ける「ヴェイン」の本質を探究することであり、ランウェイショーを必要とするのかどうか、という広義的な意味合いにさえ感じさせ、結果的にそれが何故、擁し、要されるのかを態度で示していたと感じさせた。

VEIN SS2024
だが、時代の流れは重石の如く、ダイバーシティとかサステイナブル、Y2K、クワイエット・ラグジュアリーとかいう概念がデザイナーたちに対して漠然とした閉塞状況に追い込みかねないまでに、創作に口を挟んでくる。ましてや場外ではセレブマーケティングを主体にした報道や各所記事の柱となっており、束縛条件下に置かれたように追い遣られてしまう。だが、榎本は規律も統制もなく、ただ寄り集まっているだけの集団とは訳が違う。むしろ彼はアトリエという彼の小宇宙に文字通り回帰し、彼の多様を存分に富んだ場所にゲストを招待した。

VEIN FW2024-25
document-VEIN FW2024-25- 01
多種の化学薬品が一つの小さな器に混入されたような様相とでもいえるだろう。そこには薬品の化合とは決定的に異なる過程がある。即ち、それらは、化合することを拒否しているのだ。否、拒否するという消極的な態度に留まらず、自己のアイデンティティー、明快なスタイルを積極的に主張しようとしているのである。

VEIN FW2024-25
2024年2月5日、パリメンズ期間中の現地での展示会を終え、帰国直後に開催された2024-25年秋冬のランウェイショーは前回の「ヴェイン」新章の続篇と位置づけすることができる。榎本は同一性(アイデンティティー)と共時性(シンクロニシティー)の親密な関係、即ち自己と他者の距離感を再考しているように感じさせる。それらを深耕した結果、「スタイル」に行き着いたかどうかはまだ榎本自身も腑に落ちていないであろうからさておくとして、私見ながら人と人との関係性、人とモノの結び付き、そしてそれらの出会いやそこで織り成される対話は榎本なりの美学とアピール、ジェスチャーであり、自身が魅了される装いというパッケージの一部だと感じる。

VEIN FW2024-25
document-VEIN FW2024-25- 02
それはファッションという領域を超えた個人的な表現、上述(美学、アピール、ジェスチャー)の審美的で普遍性の魅力を「ave」というパッケージとして提供しようと試みたのではないだろうか。


VEIN FW2024-25
本作のテーマは「ave」。「歓迎」「敬意」の意のラテン語である。「ヴェイン」を「ヴェイン」たらしめるための、より「いま」の親密さをひとつひとつ深めていく、その出発点であるアトリエに自分たちは存在し、ゲストと共有したい、というこれは正しく榎本の宣言であり、ある種の約束に他ならない。「構造表現主義」に向き合ったり、自身の琴線に触れたアートから着想を得る、という殆ど正統の位置に取って代わりかねない有り様であったことに徴すれば、この「歓迎」「敬意」と云う初心は、ハッとさせられるマニフェストでもある。コレクションノートには次のように記されている。「人と人が互いを認識し、交流をはじめるときのきっかけである“挨拶”は、ごく平凡な行為でも、人生のなかで無数に繰り返され、小さなコミュニティから文化圏までのそれぞれの特性を表象さえするのではないだろうか?そう思案した榎本光希は、2024年秋冬コレクションにおいて、ブランドやコレクション、ひいては一着の衣服と、着るひととの関係を構造的に見つめ直し ながら、そのうちに育まれうる、未来志向で、人肌を感じられる関係性を眺めていきました」。また、「これは、ブランド、デザイン、クリエイターとの協業、そして ファッションショーを介した、ごく小規模なコミュニティのあり方と親密さに関する実験でもある のかもしれません」とも。

VEIN FW2024-25
今季を通貫するのは、一人の個人に内在する実験感覚である。創作を指揮する個人の意識と、それを更に具現するアトリエとクリエーティブチームという集合の意識。そこには、奥深い思考とリサーチが詰め込まれている。ただ美しく装い飾ったり、削り落とすのが最終目的ではなく、試行錯誤の結果、自ずと必要のない肉が落ちて根源的な純粋さが炙り出されたに過ぎない。この間、一貫した「ヴェイン」の葉が脈と成っていく様を「主」とし続け、個人の口語は「従」としていくその姿勢は守り続けている。それは一種の構造表現ではないだろうか(いずれ本人に確認してみたい)。

独り善がりな物語や人物像に縋るのではない。終始一貫したオブジェクトの実質が曇りなく現れた上で、作者たる榎本の台詞が囁かれているかのよう。これは様式としてのクラシカルではないが、意識としてのクラシカルというものではないだろうか。まず本質的なプロットがあり、それを紡ぎ、それに呼応するかのように榎本の言葉が聞こえてくる。物語は刺激的だけではない、という事実をこのショーではまざまざと実感させられる。榎本はミニマルなデザイナーと評されることもあるだろう。単純な削ぎ落としをそう称すことはあるだろうが果たしてそれだけなのだろうか。そこには本質と徹底して向き合ったことで見えてきた案(イメージ)と思索(アイデア)を詰め込んだ濃度の高いデザインといえるに他ならない。
document-VEIN FW2024-25- 03