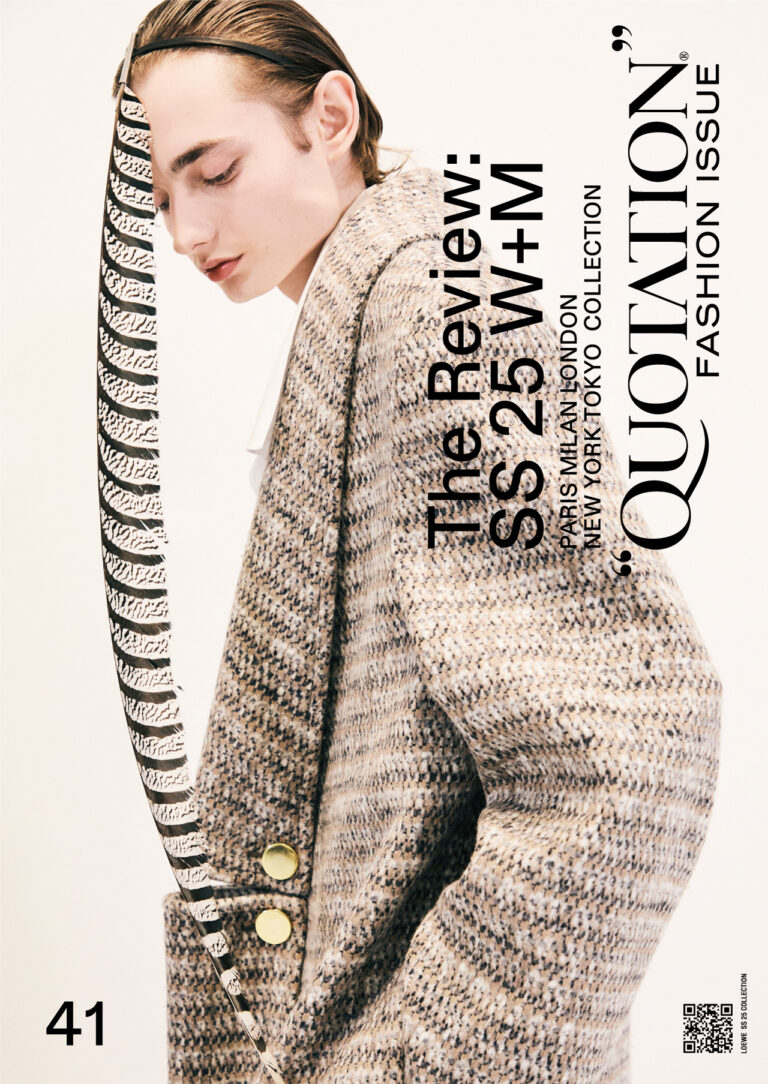FEATURE|映像がブランドの構築に必要となる時代に向かって|前篇

写真左から阿部龍太郎、汐田海平、山田佑樹
経営やそれに伴う戦略が多角的になりつつある現代。
それに纏わる実業家同士の対話は成立したとしても、それがそのままカスタマーに浸透するとは限らない。パンデミックを経て、著しく物事に対して懐疑的になっていく中で、何を視点にすべきか、はタクトを振るう者たちの手腕が問われる。
本企画では、映像というあらゆる要素を包括した総合メディアを通して、ブランド構築に向かう実態とその可能性について思索する。
ディレクション、プロデュースといった今では耳馴染みの良い肩書きを背負う者たちがどのような視座で実業に向かい、そして映像に対してどのようなアティチュードで接しているのか。前篇では、各々の立ち位置から見たコミュニケーションの在り方、映像とブランドの関係性を中心に交差してもらった。
出会いと交わった意外なきっかけ
――これまでのキャリアと、現在それぞれの会社のミッションや自身の立ち位置について。また、どのようにして他の二人と出会ったか?
山田佑樹(以下、山田): 僕はNEWPEACEという会社に所属していて、ブランドディレクターという肩書きで働いています。企業や商品、行政のブランディングに欠かせない戦略コンサルティングと、クリエーティブディレクションを担う職種です。NEWPEACEにはIWAKANやONFAdd、FLAG21といった所属メンバー中心の自社コミュニティーもありますが、その先端アクションの知見に触れながら、僕はクライアントのブランドやコミュニティーの支援をしています。今年PRONIという会社のブランディングを手がけたことがお二人との出会いのきっかけでした。PRONIが提供する「PRONIアイミツ」はBtoBのビジネスマッチングサービスです。BtoB(企業間取引)にブランディングは必要か、という議論が長い間なされていますが、今は個人が消費者として過ごしているか、企業人として過ごしているか、は時間としてもスタンスとしても溶け合っています。最終的に個人に届くという点では同じなので、PRONIチームと私たちはブランディングが欠かせないと考えたプロジェクトでした。BtoBサービスは特に複雑なカスタマージャーニーが描かれます。経営陣や僕らのようなブランドコンサルティングの立場からしたら重要視されますが、これを顧客とのタッチポイントに持っていくのが至難の業で、スライドで何ページにも及ぶ内容が、ウェブサイトにあったとしても当然見てもらえない。UGCがこれだけ重要な時代では、一方向で「好印象を抱いてください」というPRメッセージだけでは、届かない。BtoBサービスのカスタマージャーニーをユーザーへ届けるために、映像がメディアに向いているなと漠然と考えていました。最初はビジネスパーソン向けにタクシー広告を作る案などが出やすいですが、CM映像ではなく、ショートムービーである種の個人のドラマを描くことで、顧客像を描けないかと。そこで相談したのがシェイクトーキョーの汐田さんでした。僕と汐田さんともう一人映像プロデューサーの方で話していく中で、これはやはりCM映像ではなくショートムービー的に作る必要があるね、という話になり、開発体制も企画や絵コンテから書くのではなく、ロングシノプシスという脚本の骨子となるあらすじから書き始めたりもしました。この蓄積がショートムービーを作るべきだという確信になり、PR的な要件が求められているプロジェクトの状況の中で、ショートムービーを提案しました。提案の結果、それに共感して頂き、PRONIチームと二人三脚で映像を作って、今は広く見ていただける状況です。ブランディングに映像はつきものですが、単なる流して終わりのものではなく、ウェブのトップにも使われるなどブランドの顔つきの一つになりました。その映像をリリースした翌日にショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA)でBRANDED SHORTSというブランデッドムービーのプロジェクトを担当している阿部さんが是非映画祭に出してもらえないか、と連絡をくれました。
汐田海平(以下、汐田): そうでしたね。僕はシェイクトーキョーというクリエーティブスタジオを経営していて、経営者としてだけではなく自らも映像のプロデューサー、制作に携わっています。元々は10年以上映画プロデューサーとして働いていて、自分ないし自分の会社で出資して作った長編映画も3本あります。そういうオリジナルコンテンツを作る経験の中で、届けることもやり始め、コンテンツや場所を作るような仕事をしていました。その後、他社の映画の宣伝を手伝ったり、イベントを開催したり。最近は更に派生させて、一般企業や地方自治体のSNS周りのショートムービーをプロデュースしたり、動画を中心にしたコンテンツ、場所作りをしています。阿部さんとの出会いはかなり意外で。
阿部 龍太郎(以下、阿部): Clubhouse(音声SNSアプリケーション)が、まさに流行ろうとしているアプリだった時期に、僕も汐田さんもヘビーユーザーで、そこで出会いましたね。
汐田: はい、映画業界のインフルエンサーとの交流もあったので、結構規模の大きい映画好きのルームを設けてお話していましたね。コンテンツについてだけではなく、コロナ禍で映画館も閉鎖を余儀なくされていたので、業界のシステムについての話が多かったと思います。
阿部: 当時は招待枠も少なかったからか、個性の強い人が集う場所でした。僕はその中で、いくつかのコミュニティに定着して、映画好きのコミュニティの中に汐田さんがいらっしゃいました。たまに企画も設けられて、例えば俳優の斎藤工さんもヘビーユーザーで、参加されていました。その後、汐田さんは試写会も主催されているので、そこに伺って、Clubhouseでお話した阿部です、とご挨拶したのが最初でしたね。
汐田: あの時のClubhouseは面白かったですね。
阿部: まさに瞬間風速的なトレンドで爆発力はありました。
山田: Clubhouseがふたりの出会いのきっかけとは知りませんでした。
汐田: 阿部さんは当時映画のお仕事はされてなかったですよね?
阿部: そうです。汐田さんとClubhouseで初めてお話した時は、ITのベンチャー企業で営業をしていました。色々な理由はありますが、一番の理由は新型コロナウイルスの蔓延で、人生を見つめ直していた時期と、Clubhouseで自由に幅広く色々な活動している人々と出会えたことが大きなきっかけになったと思います。会社を辞めた後、今のSSFF & ASIAという国際短編映画祭を主催している株式会社ビジュアルボイスに入社しました。SSFF & ASIAだけではなく、その他のイベントのプロデュースやショートフィルムの配給や制作、プロデュース、他にもNFTなどを活用した知財管理、マーケットも手がけています。SSFF & ASIAは今年で25周年を迎えました。アメリカのアカデミー賞の公認になっていて、グランプリ=ジョージ・ルーカスアワードを含む5つの受賞作品が翌年のアカデミー賞ノミネートの権利を獲得できる映画祭です。日本の映画祭でアカデミー賞公認は3つの映画祭のみ(2023年10月現在)で、SSFF & ASIAの5作品を推薦できる立場は、アジア有数となっています。僕はプロデューサーとして企画立案、制作、営業、他にもNFTにおけるビジネス領域にも参画しています。会社のコアメンバーは10人前後なので、全員がそのような動き方になっています。


PRONI株式会社ブランドムービー「プロってなんだろう」

映画「西北西」ポスター

SHORTSHORTSがNTTと制作した映画「NEO PORTRAITS」/ ©️2023 Pacific Voice ALL RIGHT RESERVED.
未曾有の事態を経て、変わったこと変わらないこと
――パンデミックが収束に向かう中で、それ以前と以後でコミュニケーションのあり方は変わったと思うか?
阿部: オンラインとオフラインの議題は避けられません。コロナ前は広義的な意味でのコミュニケーションを取る際に、当然オフラインが前提で、オンラインを始め他の手段を考えたことがなかった。ただ、コロナ禍ではオンラインの時代になった。特に若い世代は、高校大学などで僕ら以上に制限されていただろうし、僕らとは一挙手一投足がまったく違う。彼らはオンラインが当たり前な時期に多感な時期を過ごしたと思います。そこでオンラインの長所短所を全てインプット・アウトプットした後、今はそれぞれの行動コミュニケーションによって、敏感に識別されるようになった。複数人集まる際に、移動を考慮するとオンラインの方が効率良い。ビジネス領域では特にそうだと思います。個人的にアイデア出しなどはオフラインでやったほうがいいのかな、と思っていますが、パフォーマンスを総合的に加味して識別し、オンラインかオフラインかを選ぶ時代になったなと思います。
汐田: 選択の基準が感染症対策から効率に移行しましたね。
阿部: その選択は難しいです。判断を迷うことが増えました。
汐田: 特にオフラインの場合、明確な理由が必要になりましたよね。
阿部: でも、それはいいことだと思います。
汐田: 先ほど阿部さんが仰っていたように、高校大学時代をオンライン中心に過ごして生きてきた世代がこれからは社会の中心になります。映画業界はそもそも非効率なのです。僕も不便さや非効率は好きなので、それは楽しいけれど一日に入れられるコミュニケーションの量や打ち合わせの時間はオンラインの導入によって、かなり増えた。それに関しては確かに価値観が変わったといって良いと思います。よりアクティブになっていて、それが新世代でも同様のことが起きると思います。オフラインは、こんなに楽しいのか、とか。僕らとはオフラインの感覚が確実に違う。
阿部: 僕らにとってはオフラインに回帰するという感覚ですが、彼らにとっては新しい感覚なんですよね。
山田: 僕は前職が多摩美術大学の教員なのですが、2020年1月に4年生と企画した卒展を、初日だけ展示してすぐに撤収した日を思い出します。あの時期を境に、大学教育も一変しました。最近、別の大学で「デザインと経営」について講義をするときに、ハードなグループ課題を出題するのですが、学生に好評で。その理由は、同級生にこんな優秀な人がいることを初めて知りました、とかなのです。出会いもディベートも彼らにとっては新鮮なので、本気で楽しんでいるし、提案のレベルも高い。



映像とブランド構築の整合性
――ショートムービーとブランディングの接点とその2軸の相性の良さについてどのように考えているか?
山田: 今日の話に、僕がお二人をお誘いした理由でもあるので、僕からお話します。まずはコロナを経験したことは、広告やコミュニケーションのトレンドも変えたと思います。それは、インターネットに記載されている情報の真実味がより落ちたことに由来しています。新型コロナウイルスという生命と科学についての情報が揃っていたとしても、どれを信じていいのかがわからない。その体験を経験した私たちは、情報を見る眼が更に変わっています。その眼に対して、どんなに華のあるタレントをCMに起用し、企業に都合のよい部分だけを伝える映像を作ったとしても、共感は生まれない。より必要になったのは、社長室や事業部で話されているような、本当に顧客体験として届けたいと願っているその生の思いを、その部屋に閉じ込めて置かないこと。僕はそれを、クリエーティブの力で外の世界に出したいと常々思っています。ブランディングプロジェクトでは、よく本も作ります。作り出そうとするブランドが、顧客や社員の日々のコミュニケーションハブとなるためには、どういう意図を持ってつくったかという、コンテクストを透明にする必要があるからです。そうしたトレンドや、時勢の中で成すべきことを表現するのに、特に優れたメディアは、ドラマを描ける映像であり、さらに広告映像ではなく、ショートムービーのような映像だと考えています。自分たちの思いを透明に描くことができ、鑑賞者の共感に思いを馳せることができるメディアだからです。その数分の映像が、その企業に勤める人が家族に自分の会社を紹介するときに役立ったりすることが、延いては顧客の共感を想像することに繋がります。ブランドガイドライン資料が、ボードメンバーだけに共有されたクラウドで数ヶ月眠っている、なんて時代ではありません。
汐田: 今の山田さんのお話、映像を通した顧客体験は僕も着目しています。例えば、広告やマーケティング、プロモーションにおける映像は逆算思考になりがちです。いつまでにこれを達成したいから最初のフェーズではこれをやるよね、とか。それは社長室での会議では、確かに理解できますが、周囲は追いついていけない。映像では上手(かみて)下手(しもて)という用語があります。例えば「マリオブラザーズ」では、主人公のマリオは左から右に進み、敵キャラクターであるクッパは右で待ち構えていますよね。絶対にマリオ側に立つ方がわかりやすいのです。何故映像がブランディングに向いているかというと、人中心にストーリーが進むので、左から右に進みやすくなる。そうなると、社長室で考えていたことが顧客体験を通じて浸透していく。理解してもらうためのガイドラインのように且つガイドラインとも感じさせず、恰も体験しているかのような感覚を得られる。その橋渡しになります。見返すことはできるけど、行ったり来たりしない。一方向の表現だからこそ、ブランディングと映像は噛み合うのかなと思います。
阿部: 弊社の話になってしまいますが、SSFF & ASIAの中にBRANDED SHORTSという部門があります。そこでは企業や自治体が制作するブランデッドムービーを募集しています。Branded Shorts of the Yearナショナル部門とインターナショナル部門の優秀賞を審査員たちと協議する他、Indeed Japan株式会社との協業で、HR(Human Resource)部門 supported by Indeedや観光映像大賞のカテゴリーもあります。ビジュアルボイスが企業や自治体と一緒にブランデッドムービーを製作したり、映画祭の中で発表したりもします。簡易的に羅列しましたが、どのような人や会社にも必ず物語がある。我々は自社をモノガタリカンパニーと説いているのですが、その物語をビジネスにしていくことが大きなミッションです。また、CMは流されてしまうため、見られるコンテンツとして、宣伝でもなくプロモーションでもなく、ブランディングが必要なのかなとも思います。それは、コンテンツとしてブランディングを成立させなくてはならない時代になっているということでもあると思います。人との繋がりもネット上に求めている時代において、資料を淡々と閲覧させるのではなく、共に感動するためのコンテンツを作らなければなりません。我々エンターテイメント業界だけではなく、どんな企業でもその会社のファンになってもらう必要がある。好き、共感を生むためには物語は最も適していて、それをいろんな感覚を独占しながら伝えることができるのが映像の長所だと思います。
後篇は近日公開