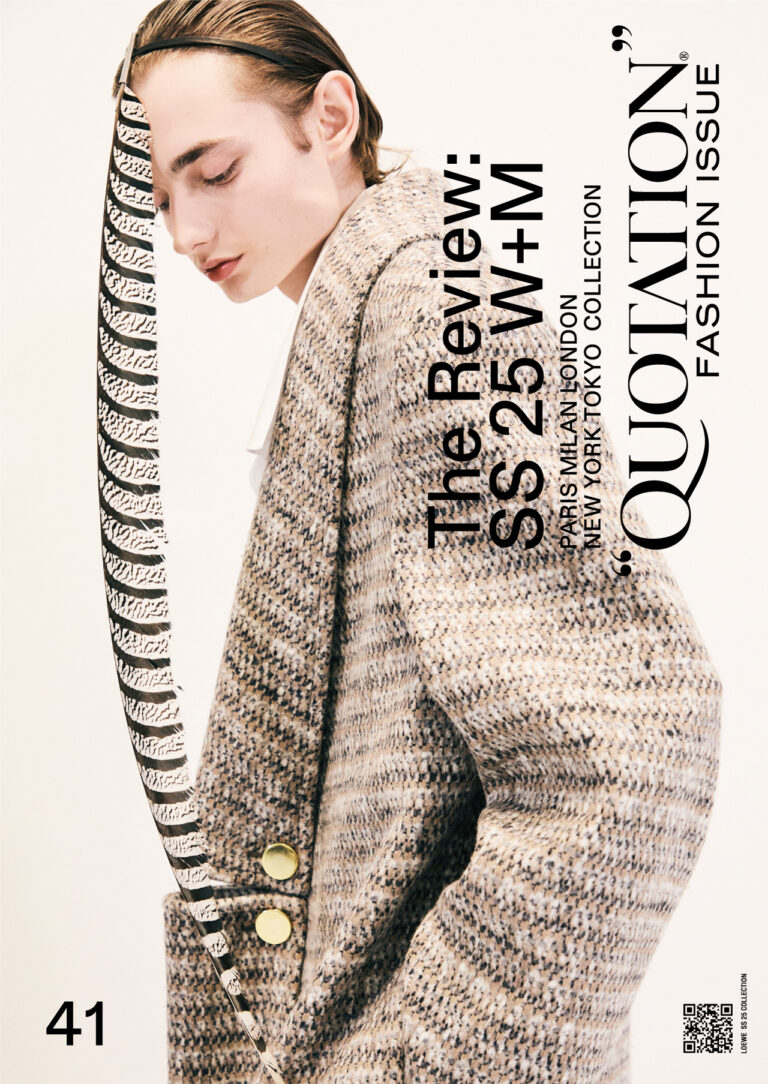FEATURE|「mister it.」”open fitting”

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
我々は自分たちの生活が便利になればなるほど、夢や旅、あるいは自己表現の手段とか、そのひとの個性やオーラによる表現に重要性を見出そうとする。そうなると服というのは、我々のこうした知的で精神的な探究のパートナーになり得る。他方、服の作り手は?彼らの志向は、日常に帰結する。
現代性と日常性に通底する志向を標榜する「mister it.」の砂川卓也は、「身近なオートクチュール」の具現に勤しもうともモードの伝記を感傷的に語り、頌歌したいわけではない。彼は語るべき対象(このブランドの場合は砂川の身近な人物)に密着し没頭するのではなく、固有の時の連関を念頭に置きながらも、過去を継承、反復させるよりは、そこに新たな「何か」を加えることに重点を置いている。 それが、自身にとって初めてのランウェイショー形式での発表となった2024-25年秋冬は「couture rhythm」だったのだろうし、今回でいえば“open fitting”に当たる。「前回のショーの主題になった「couture rhythm」は僕の創作における根底にあるもの。ショーを通してその一部を披露できたと思います。今回はそれを土台にプレゼンテーションをしたいという思いがありました。そこで、デザインプロセスの中で最も重要なエレメントの一つであるフィッティングを公開しようという流れに至ったわけです」と砂川は語る。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
2024年9月14日、舞台となるTEN10スタジオに本番前(この場合何を以って本番なのかわからなくなるが…)に行くと「mister it.」のチームは招待客に配布する型録冊子やルック毎の説明が流れるアナウンスの音響や進行チェックをチーム全体で共有している。だが、砂川の口数は少ない。どうしたわけか。「意識して口数が少なかったわけではないですよ。普段から饒舌なタイプではないですから(笑)。本番もそうでしたが、自然体です。フィッティングが終わった今振り返ると、7年前にパリで着想となった10人の身近な人たちを招いて初めて「mister it.」を披露したあのプレゼンテーションと被る瞬間が多々ありました」。砂川のこうした個人的な思いは他者が想像しがたい印なのかもしれない。
今回の“open fitting”は約7年前、日本に帰国する前に発表した「mister it.」のコレクションのプレゼンテーションがインスピレーションになっている。その時はモデルを2人用意し、招待客は着想となった10人の身近な人たちのみ。順番にその場で着用してもらいながら砂川は語りかけるようにプレゼンテーションしたようだが、今回は始まる前に砂川自身が登壇し、今回のコレクションの真意と自身の創作道徳を招待客に説明した。「パリでのプレゼンテーションは『あなたにはこういう癖があって、こういう人だからデザインにしてみました』とか話した覚えがあります。そういう些細なことを日常会話調に話しながら。その10人は前に務めていた会社の同僚で、今でもリスペクトがあります。今回招待させて頂いた方々もリスペクトがある身近な人たちを中心にお招きしました。当時と今の境遇が被る部分もありますし、そういう人たちの前で自分の気持ちを話し、作った服を見せる緊張感はシンクロしていたと思います」。
招待客に配布された手作りの冊子には、フィッティングで登場した全21ルックの説明書きと一人一人異なるページに付箋が貼られている。例えば、筆者に配布された冊子に貼られていた付箋はルック9のSylvia dress。「Sylviaの家にあったテーブルクロスから着想を得てデザインしました。彼女はインド出身。そのテーブルクロスもインドで入手したもの。実際にこの刺繍もインドの職人さんの手によって一つ一つ仕上げています」と書かれている。「mister it.」のデザインに相応しい真っ白なレース地を変型カットされたシンプルなドレスワンピースは手仕事の生な感覚と人の生活の香りに美しい裁断術が施されている。一着一着を積み重ねて階層化させ、そして現実の中にクチュールの息吹を靡かせる普遍的な洋服。筆者の冊子に何故、このルックが貼られていたのか。真意は定かではないが、このような何気無いルックから「mister it.」を感じて欲しいというブランドからのメッセージだったのではないか、と勘繰ってしまう。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
「洋服作りにおけるフィッティングとは、サンプルが上がってフィッティングして、修正を入れてフィニッシュするのが従来の傾向です。ただ僕の場合はトワル製作の段階からフィッティングをします。何回も修正を入れるし、着るだけではなく歩いてもらい、左ポケットに手を入れた時と右ポケットに手を入れた時、その時の左右のシャツの見え方…ジャケットの袖をそのまま通した見え方と袖を片方だけ通した時の見え方。それはすべて異なるので、実際に着てもらった上で明らかになるデザインのニュアンスです」。想像し得るすべての「動き」を可視化させ、果てしない作業を繰り返していくのが砂川の自然な服作りであり、フィッティングはその過程にある。そこで共演するモデルは戸惑いを隠さない。予期せぬことを想定し、完璧に近づけるのがランウェイショーだとするならば、フィッティングはポジティブな意味で肩の力が抜けている。「包み隠さずに見てもらいたかったので、モデルの表情や僕の表情もデザインの一部であること、実は即興的なことだったり、アドリブも入れていましたが、普段からやっているフィッティングの生っぽさを見てもらえたと思います」。
昨今、「アドリブ」という言葉が随分と便宜に使われている。屡々、演劇や漫才の舞台で巧みなアドリブ使いに対して台本にない台詞をその場の思い付きでこなしていると思われる。時には出鱈目さえもアドリブだと思われることもあるだろう。しかし、アドリブは出鱈目の延長線上にあるものでもなければ、ジャストアイデアでその場を凌ぐ技でもなく、考察と創造の賜物である。創作世界を壊すことなく、その強度を増長させるという歴とした役割がある。作者が気づいていないだけで(それはある種の無意識下で)、真に求めているものを認識、理解、そして共有することで初めて場に現れる。やはり徹底的な創作行為でしかない。そしてそれは「名」を通して完全に作り込んでいく過程で生まれる。「その人物像であればこうする」という提示だけではなく「それはしない」というキャンセルができるかどうか。そこまでを考えた上で空間と時間を設計している。だからアドリブは時代のパースペクティブの中で無視することなく、緻密に考え抜かれた異端な作法であって、出鱈目のような異物ではない。
逆をいうのであれば、世界観の理解と共有ができてさえいれば、あらゆるトラブルから作者を救うことができる。例えば、フィッティング中に帽子を付けずに歩き出してしまったモデルがいたとしても一旦ウオーキングをストップさせ、そして帽子を納得がいく形で被らせてから再度歩かせる。歩いていたモデルが持っているハンガーバッグにかかったシャツジャケットを次のモデルが着るはずだったのに、入れ替えがうまくいかないのであれば、ジャケットを着ずにまずはそのまま歩かせてみる。そして戻ってきたら着させて再度歩かせる。これはモデルにもその世界の認識と共有がされているが故のアドリブだったし、見る者はそのライブ感に「ひと癖」を感じたはずである。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
砂川の創作道徳における「ひと癖」はディテールやファブリック、パターンメークに取り入れられ、それはユーモアであり、フェテッシュであるとされるが今はその癖を「名前」に感じているという。「継続的に印を付けるかのように入れていた人の名前を今ではよりストレートに作品群に入れています。今回のフィッティングでもモデルの名前が書かれたカードを持って歩いてもらいました。名前にはその人の個性がよく表れていると思いますし、その人そのものでもあります。感じ方も経年変化していくし、名前は永遠に残り続ける。名前でなくてもイニシャルを入れるとか、ちょっと暗示させる含みを持たせるのも面白いと思います」。高級注文服にはルック毎に番号が付けられ、それに反して既製服では、品番がある。前回のショーでモデルの名前が刺繍された帽子をフィナーレで全員が被っていたように、「mister it.」の記号性と匿名性は表裏一体であり、常にオブジェクトとしてその場に服がなかったとしてもサブジェクトとして人と人の媒介でありたいという素直な意思表示と捉えて差し支えないだろう。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
筆者は砂川のこうした「察する」力を感じてならない。それは主に3つの力である。例えば一つ目は、「考察」する力。服飾史における設計や構造の仕組みに人の手の温もりや残香を入れ、ズレを生じさせる。二つ目と三つ目は「観察」する力と「省察」する力。これに関しては「自分が察したことで気づいた点をデザインに入れることは多々あります。傍から見ていても気づかないようなデザインのディテールはたくさん取り入れています。着想になった人たちにヒアリングとかもしたことないです。寧ろ僕が一方的にこうかな、とか考えるのが好きです。過剰な説明は要らないと思うし、そうした心地良さはこのブランドの流儀の一辺なのかな、とも思います」と語っている。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
作品群全篇に通貫する「後ろ身頃」についての解釈についても触れておきたい。最も身体や洋服の造形にピッタリと沿う丈感から、数メートルも靡いているものまでバリエーション豊かに展開。つまり、ミニマム(最低限度)からマキシマム(最大限)まで、服の形の嵩が漸次靡いていく様子そのものをデザインと相関させながら描いている。量感、丈感への挑戦、標準仕様とは異なるスペック、モジュラー形式の設計、そして芸術的なドレーピングを流儀など、砂川はコンセプチュアルな創作を継続している。「実」(身、即ち身体)と「殻」(外観、即ち服の形)に向けた今回の言及にも、その志向は通底している。

mister it.”open fitting” Photo: Courtesy of mister it.
そもそもクチュールとは、膨大な時間の堆積に喩えることができるだろうし、時は痕跡を残すもの。それは伝統についての様々な参考文献を通してのみ得られるのではなく、まさに匠の技の蓄積に容易く見つけることができる。だが砂川は、それだけにもたれかかろうとしていない。既製服の概念の中で、「フランスの伝統的な工芸技術に委ねながら、自由で開放感のある創作意欲。脱構築と云う前衛に大きく振れようとも、着る側の身体性を蔑ろにしない思慮深い創作道徳。刹那的な衝動ではない永続的な価値を付加しようとする創作的試み」が彼の中にはある。変容の過程を伴いながら多様に変化していく洋服の「動き」に照準を定めている。寡黙な語り口ながらも懸命に口語にしていく。それはレンズやカラクリを使うわけではない、己の肉眼で見てきた日常の中で見据えた癖がある。それは芳香となって見る者を穏やかにさせてくれる。