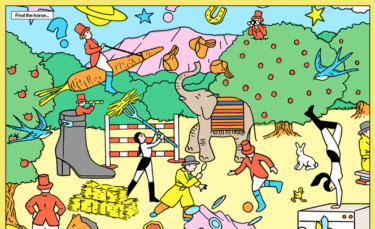FEATURE|session02 クリエイティブ・ベース「TEN10」に内在するアナログ的なベースメントの蓋然

TEN10 Co.,Ltdのコアメンバー(左からスタイリスト立松秀顕、市野沢祐大、PR志賀光)
衣装や映像、デジタルコンテンツのデザインや製作、PRマーケティングなど幅広く手がける「TEN10(テン)」。その新たな拠点として、「オフィス」「スタジオ」「ラボラトリー」が一体となったクリエイティブ・ベースが渋谷区代々木にひっそりと誕生した。中心となるメンバーは、スタイリストの市野沢祐大(CEO)と立松秀顕(取締役)、そしてPRの志賀 光(COO)の3名。各々の領域で活躍してきた3人が、なぜ今ひとつの場所に結集し、共に同じ道を歩むことになったのか。また業界を跨いだあらゆる人材が行き交うクリエイティブ・ベースにはどのような可能性が秘められているのか。3人の出会いから現在のクリエイティブ・ベースのこと、そして同時に運営するビストロ「iiiio(イオ)」や、茨城県にある第二の拠点について話を聞いた。

出会いときっかけ
―それぞれの出会いについて
立松秀顕(以下、立松):今はアーティストのスタイリングやディレクションを中心とした仕事がメインになっていますが、それはアシスタント時代からの下地があったからかもしれません。ただ、所謂スタイリストのアシスタントではなく、アーティストのマネージメントやクリエイティブを管轄する企業から仕事を内部で請け負う部署での下積みだったので、市野沢の仕事柄とは毛色が違いますね。志賀とは彼がPR01.(株式会社ワンオーのプレス事業部)で勤めていた頃からリースの対応を通して知り合っていました。市野沢とは独立後ですね。当時僕らがお世話になっていた会社がシェアオフィスを構えていて、同じ作業場で時間を共にしていました。
市野沢祐大(以下、市野沢):僕は20代前半から後半までアシスタントをやっていて、独立前から二人と出会っています。仕事内容というと、最初はメンズのスタイリングが多かったです。他にもウインドウのデザインやコレクションのイメージやビジュアル作りなどを手がけていましたが、仕事量はそんなに多くなかったのでロケバスの仕事とかをして食い繋いでいました。当然、今のようにやりたいことが形にできるような立場ではなかったので、自分たちの志向の話をしていました。そういう時期に自分たちの根本を共有できたことは今のTEN10の取り組みに繋がっていると思います。立松は雰囲気もキャラクターもあったし、それは今も変わらないと思う。
立松:そうかな(笑)。そういえば、3人で集まる機会って当時からほぼなかったよね。各々では会っていたけれど。
志賀光(以下、志賀):僕は二人とは別々で会っていたし、市野沢と立松も会っていた話は聞くけれど、3人で会ったのってだいぶ後だったね。
市野沢:スケジュールを合わせるのも大変だったしね。
志賀:僕は二人に比べると独立はだいぶ後になります。振り返ると大学卒業の時期は特にやりたいことがなく、とりあえずたくさんの企業の面接を受けて、採用をいただけたのですが、中途半端な気持ちで仕事に向かうのは危険なので、全て辞退して。その後、バンタン(デザイン研究所)に入学したのですが、すぐにインターン先を紹介してもらって、半年間prospere(有限会社プロスペールはファッションのプレス、マーケティング業務を中心にメディアコミュニケーション事業を展開するPR会社)で働き、満期を迎えて、次は紹介状書いてもらってPR01.でインターン。翌年にはアルバイトとして入社し、のちに正社員になりました。独立前に、既にTEN10の前身となる、会社というよりもクリエイターチームのような集団は作っていました。それはフォトグラファー、アートディレクター、ファッションデザイナーとか領域を跨いで色々なモノづくりに取り組もうというもので、僕らの世代でそういうことをやっている人は日本ではまだ少なかったと思います。自腹を切って自分たちが面白いものを作るのではなく、ビジネスとして成立させるために株式会社TEN10として発足したのは2021年。その頃からTEN10という名前でしたし、事務所もありました。


―TEN10の名前の由来は?
市野沢:もともと僕の中では、軸を表す「点」と、中心となる「点」という2つの意味を合わせたTENと10を暗示させています。出発から目的までを全てそこで完結できる場が欲しかったのと、衣装とかグラフィックとかそういうディテールも纏めて同じ場所でできたら良いなという流れの中、じゃあそういうクリエイターのマネジメントにも取り組もうという流れになりました。
―TEN10発足後、各々の本流に影響があったシーンは?
市野沢:ファッション系の専門学校の講師を務めているのですが、コロナ禍の影響で優秀な学生が就職難に悩まされていたこともあって、TEN10内部にラボラトリーを作りました。ファッション業界は結局、ファッションウィークを始めコロナ禍で歩みを止めなかったですよね。確かに2020年の春くらいは流石に何もできない日々でしたが、5月ぐらいからは自主的に動いていました。僕らもサブミッションではないですが、モデルを使わず最小人数のスタッフだけで作品撮りをしていました。それを雑誌『装苑』で特集してもらったりしていたら、業界内でも知れ渡ってコミュニケーションが生まれた気がします。
立松:情報交換は有意義ですし、ウチの場合、内部でチーム作りもできてしまうので、個人では扱いにくい大きい案件とかを運用していくアプローチは他にないかもしれません。例えば志賀と仕事を一緒にすると、僕というスタイリスト個人では扱えなかった案件を成立させることができます。そういう事例は増えましたね。ビジュアルディレクションをスタイリストの視点ではなくてPRの視点で、マーケティングやプロモーション目線からの提案を伝えてくれたり。しかも企画段階から一緒に作って提案を進めることで、対企業に対して多角的に提案ができるんです。僕らは決まった枠組みの中でスタイリストとして配置されることが多いのですが、その枠組み作りから提案ができたり。今はそういう案件も増えていますが、当時はまだ少なかったので、斬新に感じるクライアントが多かったと思います。
志賀:自分の仕事のアウトプットはかなり幅が広がったし、同じ場所にいるから教養を蓄えることができます。お互いの知識をインプットし合って、個人の仕事でアウトプットできる体制が面白いなと思っています。本質的には、PRもスタイリストも、コミュニケーションを作るためのツールを作る仕事です。だからファッション業界に留まらず、領域外でも通用するような媒介を提案するとか、潜在的にそういった共通認識が3人の中にあると思います。スタイリストやPRが、スタイリングやプレス業務しかしないなんてことはなくなってきつつあります。現場に行けばスタイリストが撮影のディレクションをすることもあるし、 PRがキャスティングや制作に携わることもあるからです。その曖昧さに歯痒さを感じていたのは確かなので、この人は何をやっているの?という状況を顕在化させて分解し、各ポジションを明確にする。その上で、案件毎に同じ人物でも立場が異なる状況を自然に作る。そういったことに対して僕たちは発足当初から取り掛かっていました。なので本流の仕事から見直している感覚です。常に疑う目線は重要だと思っています。


クリエイティブ・ベースの誕生
―新たな拠点であるこのクリエイティブ・ベースは、「オフィス」「スタジオ」「ラボラトリー」が三位一体となっているが、それぞれの狙いは?
立松:内的な話でいうと、年々仕事のスケールが大きくなるにつれて、拠点も増えていき、コミュニケーションが円滑に取り辛くなってきていました。そこで、やはり大きな拠点を構えよう、ということになりました。外的な話でいうと、発信の仕方が大きく変わったと思います。取り組んでいることだけではなく、場所として説得力も増したと思いますし、目に見える形が最も伝わりやすいです。まだ構えてから5ヶ月ほどですが、既に多くの人が出入りしているので、想像以上だと感じています。
市野沢:こういう場所があるとイメージも膨らみやすくなるし、どのように仕事と自分という個人の目線を合わせるか、またその両軸をどのように膨らますか、ということを考える機会が増えました。例えば、自分がスタイリングを手がけているアーティストも衣装だけではなく、撮影まで全てここで完結させることができる。もう一つは立松の話にあったように、対外的なコミュニケーションがここで取れるということです。9月中旬に「mister it.」がここでプレゼンテーションを開催したのですが、ここでこういうことができるのか、など外的な力が上手く働くことによって新しいイメージを構築することができたと思います。
志賀:もっと色んなアプローチができると思います。ただ、クライアントワークからもう少し拡張していったワーク……例えば、繊維業界だけではなく、学生支援にまで行き届かせるとか、完結できることだけが重要なのではなく、可能性を感じてもらえる場所を作る、ということができたという実感があります。個人的に、現代において如何に企めるかは非常に重要だと思います。それは僕らだけではありません。オープニングの内覧会も、他のPRエージェンシーにもサポートしてもらいました。彼らには、まだ工事中だったこの場所を見に来てもらいました。そこで、各々が持っているクライアントだったらここで何ができるかを想像してもらったり。他の職種の人たちも然りです。PRの手法の中心となっているメディアやインフルエンサーに発信してもらうこと、そういった施策のみでは現代的だとは感じません。今は企み上手な人たちがここで既に仕込み始めている段階です。一つのブランドに対してそういうことをやりたいというよりは、複数のブランドが一緒になって新しい企みを生むことができるきっかけを作っているような感覚です。僕自身、ブランドと月額の契約をしているわけではなく、固定のブランドだけをPRしないような仕事のスタイルを保っています。リスクはありますが、他の関係者と関わりやすいです。インハウスPR(ブランド内部のPR部門)のセカンドエンジン的な役割でいたいといいますか。知名度はあるけれど、新たな一歩が必要なブランドって東京には数多くありますよね。そのために、展示会とは別の形式でここで何かを発表するとか、カクテルパーティーを開催するとか、コンテンツはさて置き、ブランドの新しいステップのPRとして一緒に組むことができる場になればと思っています。それは自分の理想のPRなので、そこに一歩近づいた実感はあります。

ビストロiiiio(イオ)について
―ビストロiiiio koenjiについて。飲食店を始めようと思ったきっかけは?
市野沢:僕は茨城県出身なのですが、実家で米を作っていますし、友人が農業を営んでいたりしているので、食は興味の一つでした。コロナ禍でお店が潰れていたりして、周囲の人たちが苦しんでいる姿を間近で見てきて、力になりたいという気持ちがありました。iiiioは所謂飲食する場所ではありますが、このスタジオのような出会いの場になればと思っていました。野菜や魚は直納で、お酒や食器類も作り手のこだわりを感じることができるような。食を通したきっかけ作りになればと思っています。そういう「本物」を味わうことができる場所というコンセプトはオープン前から明確でした。食はリアクションが瞬間的に伝わるじゃないですか。そういう体験を増やしたかったし、僕自身の嗜好でもあるヴィンテージの家具やアート作品に囲まれながら、美味しいものを食べることができる場所はなかなかありません。そういう経験ができる空間を作っています。1階は和をモチーフとしていて、2階は北欧の温かみのあるような空間になっています。
立松:僕と志賀は市野沢の意気込みを直に受けていました。当時コロナ蔓延の真っ只中で、僕も感染しましたし、市野沢に至っては重症化して2週間くらい入院していました。退院してきたと思えば開口一番「飲食店をやろうと思う」と。結構驚きました(笑)。
志賀: 「飲食店を構えること以外、考えられない」みたいな熱量だったよね(笑)。収益など経営面を踏まえると段階を踏むべきだったので、僕も立松も冷静になって「どうやって運営していくの?」と聞いたら、「どうやってやるとかではなく、やるんだよ」みたいな(笑)。そこまでいうならと思ってすぐ動きました。その話し合いが2021年10月で、12月くらいに物件を見つけて借りて、内装に取り掛かったのが1月。オープンしたのは2022年4月。ノンストップでしたね。
立松:市野沢の話を聞いていると、動機や目的、コンセプトは明確だったので、疑問はありませんでした。
志賀:渋谷周辺の裏路地にバーを開店させる、とかだと諸先輩方がやってきていたので、同じことをやっても面白くない。あんまり行かない土地で、しかもエモーショナルな雰囲気のある高円寺で、東京ではなかなか味わえない食事を堪能できる。
市野沢:TEN10も発足していたので、繋がる脈が増えていく確信もありました。高円寺は固有のカルチャーがバックグランドにある場所なので、TEN10と絡めてビジネスもできるし、iiiioをフィルターにした新たなコミュニケーションが生まれる可能性も感じていました。
志賀:何より始めた当初から今もずっと楽しいんです。20代の時に感じてきたような何の経験もない領域に向かって知りに行く体験を今も味わうことができる。しかもPR目線でいうと食は非常に大切な要素です。以前、とあるブランドの新作の発表を兼ねて、それに関連したコース料理を作りました。メディア戦略として記事にしてもらったり、動画を作ってもらったり、SNSにポストしてもらうだけだと画一的になってしまうので、コミュニケーションツールとして食を媒介にすることは非常に効果的だったと思います。

ベースメントとコミュニティー
―ベースメントとコミュニティーの違いに関して。そういった集団化は馴れ合いになっていく危険性を含んでいるが、どのように考えているか。
立松:もちろん弊害も危惧しています。相互理解が深まれば利点が生まれますが、その反面アイデアが枯渇したり、表現が偏ったりする現状は僕らだけではなく、散見されます。あとは、予算やギャランティーが後回しにされやすかったり。この場所はコミュニティーというよりも、やはりベース的な捉え方をしていますので、入れ替わり立ち替わり人が出入りしているので、情報交換したり、意見や考えが浮遊しているので、何をキャッチするかは個人によるかと。
市野沢:スタイリスト業界に関しては、新たな発展が生まれにくいのが現状です。僕もそうですが、師匠がいて、そこで下積みを経験して独立する。そしてアシスタントを雇って、彼らも独立する。その繰り返しです。しかも、師匠の色を受け継いでしまう傾向にあります。それはスタイリングの特徴だけではなく仕事の手法など細かい部分も含めてです。デザイナーにもいえることだと思いますが、そこからさらに新しい色を加えるための機会がこの業界には本当に少ない。そこで、こういうベースメントがあることによって、色々な情報や思考がエッセンスとなったり、新たな機会を得たりする。コミュニティーの危険性の要因の一つはそのコミュニティーから脱却しにくいということもあります。そういう意味ではTEN10に出入りしやすくすることを心がけています。ファッションは表層的に扱われてしまうのは仕方がないのですが、仕方がないで終わらせるのはあまりにも意に反しているといいますか。
志賀:クリエイター同士の阿吽の呼吸や信頼関係があった上での創作は然るべきだと思います。同時にそれを固定するのではなく、増やすこともできると思います。最近は異なるPRが一つのブランドのランウェイショーを協力し合って発信していくことが増えたように、コミュニティー化せずに瞬間的に協力し合うシーンが増えています。だからメゾンの仕事をした次の日には東京ファッションウイークの仕事があったり、また別の日にはアパレル企業のお披露目会に携わったり。仕事柄、この3人の中では外と接する機会が一番多いので、そういった瞬間瞬間で異なる仕事、異なる人、異なる動きをしています。チーム作りには積極的なんですけど、コミュニティ化には消極的です。そこで交差してきた人たちを集結させたり、所々で分散させるためにはベースが必要なので、一緒に仕事をしている人たちの安心材料になると思います。コミュニティー自体はネガティブに捉えていないし、そこで生まれる面白さも感じていますが、危機感という意味では、クリエイティブが固定化してくと、モダンさがなくなる。新鮮さをどのように維持していくかはシビアに考えています。
―今後は第二の拠点にして茨城県那珂市に場を設けるとのことだが?
市野沢:その場はレザー加工や家具のリペアが中心にしようという構想があります。しかもただの加工や修繕ではなく、そこでしかできない体験を通した場にしていきます。レザー職人だけではなく、鉄工職人や内装業の職人さんなど、今まで関わりがなかったジャンルの人たちをクロスオーバーさせる場所を作っていきたいなと思っています。テーマは「ポストとテスト」。変化させていくポストと、実験していくテストを主軸にしたコンセプトです。より密に、職人とそこでしか作れないスペシャルなものを密接に作っていきたいなと。iiiioでの取り組みを含め、工芸だったり民藝だったりが盛んではあるのですが、一つに落とし込むための場所がないので、新しさを生むきっかけになればと思っています。東京からもゲストを招いて、そこで新たなクリエイティブが生まれ得る場所だと感じてもらいたいです。
志賀:地方にはまだ見ぬ光景がたくさんあるので、これまでの「広がる」というTEN10の動きから、次は「深める」というフェーズに入っていきたいですね。より実験的な試みになってくるので、面白いと思ってくれた人たちには、参加してもらえるような仕組みにできたらと思っています。面白いと思われるかどうか、それは僕個人としてのキーポイントです。自分が培ってきたものを深めて、新しい可能性を作り出せたらいいなと思っています。
立松:僕らはファッションを中心としていますが、おそらくこの場所でのゴールは全くファッション的なゴールに向かわないと思います。そのようなゴールを増やすのにiiiioがあるし、TEN10がある。

「新しさ」と「教育」
―時代毎に変容する「新しさ」と教育のコミットメントは結実していると思うが、どのように考え、実践にしているのか?
市野沢:スタイリストのアシスタントはここ3年間で大きく変わってきたと思います。続かない子もたくさんいるし、目標がない子も多い。僕らの世代にはカリスマスタイリストがいて、恰好良いスタイリスト像が明確だったので、憧憬の念がこの仕事を続けさせてくれたモチベーションになっていたと思います。それとはまた違った形で若い世代とどのようにコミットしていくかは僕ら世代の課題です。アシスタントと話す内容も変化していますし、もっとコミュニケーションの手法を僕ら側から変えていかないと、ファッション業界に面白いことが生まれにくくなってしまうと思います。具体的な話でいうと、固定概念を取り払うためのリサーチです。図書館に行ってアーカイブ資料を漁るだけではなく、SNSで何が話題になっているかとか、今渋谷や歌舞伎町にどういう子がいるのかとか、実際に忙しくて行けなくてもスマートフォン一つあれば、数分で膨大な量の情報がリサーチできますよね。一見スタイリングに関係ないように思えても、それは蓄えになるんだよ、ということをアシスタントの子たちには常に話しています。
立松:僕はあまり学生と触れ合うタイミングがないので敏感には感じていないかもしれませんが、相手が何を求めているのかとか、スタイリングする対象者のパーソナリティーとか、そういうことを深く考えて提案していきます。求められているものにプラスアルファするための逆算です。なのでアシスタントには、自分たちはもう揃っていると思っていることでも更に深掘りさせます。
志賀:教育ではないですが、僕は自分の経験や知識はいろんな人にシェアするようにしています。僕の仕事はアイデアと経験を前提にした予測が中心なので、先出しした上で自分本来のロードマップを作成します。別にそこでお金をもらおうとは思っていませんし、それが企業相手だろうが、デザイナー個人だろうが関係ありません。特にPRにはある程度のフォーマットがあって、それを別の人がやっているだけだと、視野が広がりません。だから僕の方からアイデアや経験を共有することで、隙間というか、「盗めるポイント」を用意するんです。それに対して若い世代の子たちが、そのアイデアでプロダクションワークをやってみたり、イベント制作をしたり、別の形でPRの仕事をしてみたりできたら、視野が広がって良いですよね。
―今最も気になる話題、対象(人物、ブランド、現象など)は?
市野沢:専門性です。最近だと犬カフェ。しかも犬と交流するだけではなく、犬に踏まれたりするだけのマニアックなサービスもあったり。かなりニッチだと思いますが、専門性として置き換えれば、例えば抹茶だけを取り扱ったカフェとか、包丁にフォーカスしたコースに重きを置いたレストランもあったりします。専門性と究極の拘り、そして変態性はすべて隣り合わせですよね。そういう所に人が集まるというのが面白いと思います。
立松:毎朝のルーティンなのですが、海外で活躍しているスポーツ選手のまとめサイトをザッピングします。ただ、情報を得るのではなく、現地の記者の評価やサポーターの声だけを見る。ファッションでもそうですが、日本のブランドがパリで発表しても、日本のメディアに上がっている記事が中心となるので、現地での評価はなかなか見ることができないじゃないですか。それが専門外のスポーツだと尚更なので、そういう本音を見るのは生々しくて面白味を感じます。
志賀:青山にある書店…刺繍教本とか純文学を多く扱っている本屋さんです。様々な仕事をするなかで、時折、美の強さを痛感させられます。特にファッション業界はそういう部分が色濃くあるだろうし、美に対する様々な文化が定着している部分もあります。そんな時、谷崎潤一郎の小説に「美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった」といったような一節あったなと思って、ふと書店に入りました。本を探して2冊ほど購入して店を出ようとしたら、店員の人に「谷崎が好きなの?」と声をかけられたんです。それで「好きですね」と答えてから1時間半くらい立ち話してしまって(笑)。とはいっても「ここにある本は全部読んだことあるんですか?」「読んだことあるわけないじゃん」という程度の会話です。ただ、そんな会話の中で、なんでこんなに古本を集めているのか尋ねると、一冊好きな本があって、それに夢中になっていたら数がここまで増えてしまったというのです。何かに夢中になり続けている人たちは、そういう気質にあるというか、連鎖して集っていく。それは本も人もそうで、夢中になるっておそらく本人は気づいていないこともあると思うんですが、その潜在性を見つける面白さを感じました。

◼︎TEN10(テン)
東京を拠点に活動すクリエイティブ・ベース。考える→つくる→届けるまでのコミュニケーションを、トータルプロダクトとして設計する。課題と人・社会の間にある接点を、ファッション・アート&デザイン・テクノロジー・音楽など、非言語コミュニケーション分野の視点から発見し、「表現での語り」によって解決する。またTEN10の由来は数字の10以外に軸を表す「点」の意味も含まれている。ひとりひとりが点であり、集まることでも大きな点となるように、TEN10はひとつの共同体であり、同志がいつでも集まることができるような、クリエイターの居場所そのものでもある。