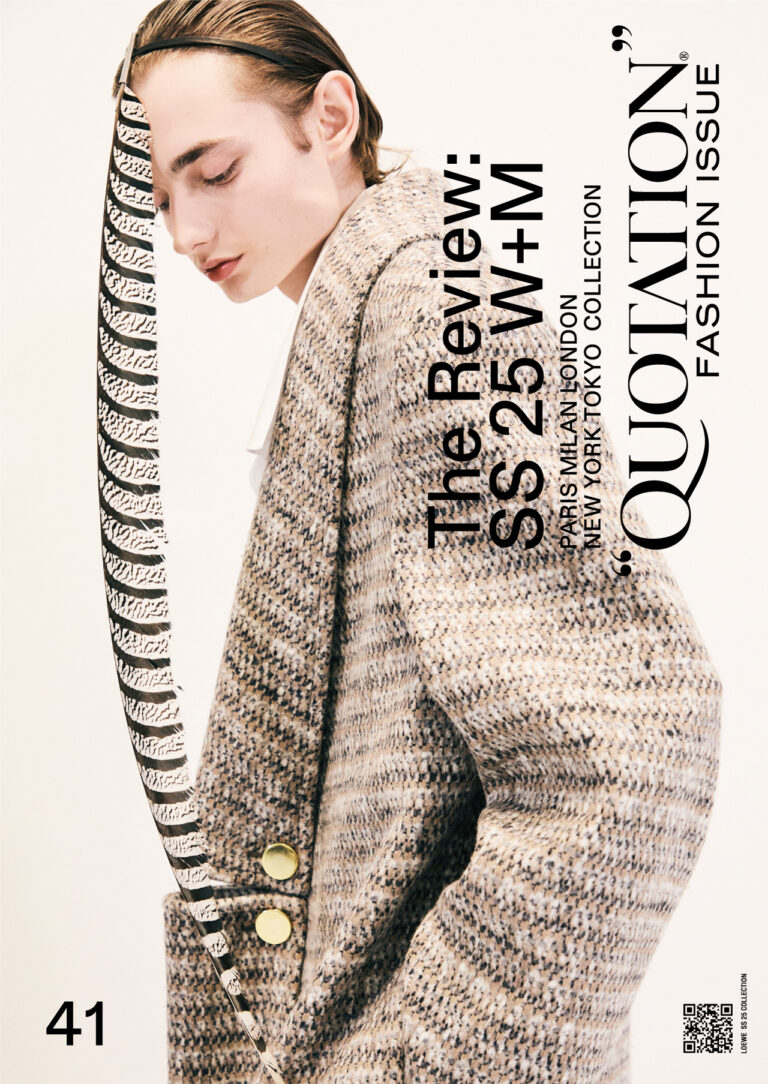FEATURE|映像がブランドの構築に必要となる時代に向かって|後篇

写真左から阿部龍太郎、山田佑樹、汐田海平
ブランドディレクターとして日々、ブランディングに欠かせない戦略コンサルティングやクリエーティブディレクションを担う山田。映像プロデューサー、制作だけでなく自らの会社の経営も手がける汐田。映画祭の企画運営や映像の配給、制作、NFTなどを活用した知財管理やセミナーなど多彩な顔を持つ阿部。三者の言葉には三様の文脈や個性がある。彼らの話はどれも夢物語でも机上の空想でもなく、現実を下地にした実直さを保つ。ビジネスというある種曖昧な領域での曖昧なやりとりではなく、体験や知覚から出る言葉は親密でありながら、時折俯瞰しており、目の前に広がる思考と実践に奥行きを感じさせる。
中核に添えた映像という表現のように、時間と空間、異質と同質、仮想と実態、媒介と直接が交差する点を進み、一本の筋道を辿る。その先に見える一寸先には何が待っているのか、何を見据えているのか。話は未来に向かって加速する。
映像表現を通した仕掛けの本質的な思惑
――議題に上がっているようなブランデッドムービーはどのような領域で、どのように発生しているのか?
阿部: CMを含めるのであれば、遥か昔から浸透しています。ただ、それが商品のプロモーションや紹介に留まってしまっていた時期が長かった。ここまでで話したような感動や面白みを感じさせたり、共感を生んだりするようなブランデッドムービーは、海外だと早い時期から主流となっています。例えば、米国とかだと20年以上前にBMWフィルムズというBMWが歌手のマドンナなど米国のスターを起用して、カーチェイスや犯罪さえ絡むようなシーンもあるようなブランデッドムービーをリリースしていました。これは、まさに映画ですよね。
汐田: 商品力に差がなくなってくると、企業のストーリーは差別化のために最適ですよね。例えば、石鹸は、どのメーカーのものも質は高い。だからこそ環境への配慮、商品の背景にある意図で判断される。それを描いたブランデッドムービーとかショートフィルムによって、共感を得たり、カスタマー基点で進めることができるか差別化ポイントになっている。また、通販を始め、商品を手に取らずに購入する際に、買い物を失敗したないためにスペックやレビューを見ますよね。ただ、今はどこのメーカーも品質は高いし、レビューも個人で発信している。そのため、ストーリーが優位になりやすい。
山田: 企業が伝えたいこと、顧客が心で抱く印象、その不和に私たちのようなブランディングファームはアンテナを張ります。プロダクトアウトか、マーケットインか、という議題も長く話されてきていますが、リアルはそのどちらでもない。顧客と企業がフラットな関係でコミュニケーションすることができるように、伝える側の印象設計がブランディングには欠かせません。
阿部: 企業は友達作りにいく感覚ですよね。
汐田: 映画の場合は、観客が対等に見てくれます。俳優や演出家は、映像を作る時、”役を生きる”という表現を使います。表現の中で生きている。映画は人生に似ているとか、旅に似ているとかいわれることがありますが、観客が対等になるために適した表現なのかなとも。
阿部: リアルに一番近い表現ですからね。音や演技、写真、建築など総合力が必要になる。映画の恐ろしいところは、一方的に撮られ、観客にも一方的に見られている、という点です。

リブランディングの社内リリース時には、大型映画館で全社員に向けてブランドムービーを放映 Photo: ©︎PRONI

映画「佐々木、イン、マイマイン」ポスター / ©️SHAKETOKYO

BRANDED SHORTS 2023 セレモニーの模様
映像と映画の相違という迷宮
――ブランデッドムービーと映画の違いは?
阿部: 今僕らが話しているブランデッドムービーには、企業や商品の詳細を出していないものも多いです。見終わった後、この会社のコンテンツだったのか、くらいのバランスで、ストーリーを持って如何に視聴者の心にメッセージを残せるか、共感や感動によって心を掴めるか、を考えます。そういう意味では、映画として作っているので、ブランデッドムービーと映画の違いはほぼないと思っています。ただ、映像と映画の違いは難しい。例えば、映画に使われているのは殆どが映像です。ただ、「ラ・ジュテ」(1962年、クリス・マルケル作)という映画のように、写真を連続させて完成させた映画もあります。他にも「EO イーオー」(2022年、イエジー・スコリモフスキー作)というロバを追い続ける映画があるのですが、ロバがメーンなので、演技も台詞もない。けれど、見終わった後にストーリーを感じる。限りなく意味のないように見える映像が連続していても映画に感じさせる作品もあります。境目が曖昧だな、と改めて感じさせられました。
汐田: 映像と映画の違いは、肉と焼肉の違いみたいなことだと思います。肉を使って焼肉を作るように、映像を使って映画を作る。別の表現でいうと、連続した写真と音をつなげて作るのが映像。また、最初から最後まで観る側が見てくれる、という期待を前提に置いた表現が映画ともいえます。なので原理的にいうと、決められた時間の中で、集団に対して限定的に映写して、最初から最後まで見ることを前提に作られた表現です。基本的に映像を止めることや、途中退席は考えられていない。対して、CMはスキップされることも想定している。
山田: 僕は映画の専門家ではないので、詳細な違いについては話せないのですが、こういう会話が発生する場こそが映像と映画の違いだと感じます。ブランドディレクターとしてプロジェクトを組成するときは、誰とやるか、に着目していて。映像で共感を生み出したいと思った時、映画に軸足を置いた議論ができる人をアサインしたい、と考えます。それは制作現場のスタッフの皆さんでも同じです。映画側がセルアウトすることは防ぎながら、映画について話せる人の中で、とある企業について話す時間を大切にする。映画というメディアの内、ブランディングや経営に有益な部分を切り取ろうとするのではなく、映画のコミュニティーの中にブランディングの話題を持っていくという意識です。そうすると、スタート地点から表現と共感のバランス、ストーリーの取り扱いを共通言語で話すことができる。だから、PRONIのブランディングで汐田さんのところにシノプシスを持って行った時は、汐田さんに共感してもらえるかどうか、が僕にとっては非常に重要でした。
阿部: 僕らがSSFF & ASIAとBRANDED SHORTSを分けていないのはそこにあります。国際短編映画祭の中で、BRANDED SHORTSをやっている理由は、映画として見て欲しいから。ブランデッドムービーはコンテンツとして楽しむ作品だと思っています。

代表のプレゼンテーションのみではなく、ブランドムービーを通じて、生まれ変わる自社を眺めるPRONI社員 Photo: ©︎PRONI

映画「佐々木、イン、マイマイン」場面写真 / ©️SHAKETOKYO
SNSから観る共感の深さ
――SNSでもTikTokやInstagramのリール(YouTubeも含)など、最短編の映像が人々の日常に与える影響は大きいが、どのように捉えているか?
阿部: もちろん利用しています。少し違うかもしれませんが、BRANDED SHORTSはここ2年程、映画祭期間にABEMAで全作品配信しています。僕個人としても頻繁に見ますし、TikTokでライブ配信もやっています。
汐田: 僕も頻繁に利用します。仕事としても地方自治体や企業のTikTok映像を作っていて、ブランデッドムービーと同じくショート動画のコミュニケーションに力を入れています。ブランデッドムービーとショート動画が対極にあるとも思っていない。手段やアプローチが違うだけです。映画は最後まで見てもらうことを前提としているけれど、見てもらえないかもしれないことも考慮しなくてはならないのが違いですね。
阿部: スキップされちゃいますからね。
汐田: 本当に面白がってもらえないと見てもらえないですから。
阿部: 見るかどうかは、冒頭2秒で決断されるといわれていますよね。
汐田: ショート動画の世界では、以前は冒頭3秒が大事ですといわれていたんですが、いつの間にか2秒になり、今では0.7秒といわれています。
阿部: 音楽もイントロがない時代ですからね。
山田: 映画とかブランデッドムービーにコミットしている汐田さんが手段やアプローチの違いを感じているショート動画に向かうというのは、どのような熱量なのですか?
汐田: ブランデッドムービーにもショート動画にも、それぞれ活躍してくれやすいフェーズや面があります。最適な手段をその都度考えています。本山を映画とした時に、そこにどのように行き着いてもらうか、が必要なことなので、それらが届ける手段の選択肢として存在することは重要だと思っています。個人的な面白味でいうと、アルゴリズムとか人の反射神経と戦いながら、面白いと思ってもらえる技術の思索は映画にも通ずる。だから結構ショート動画は好きですよ。
阿部: ごっこ倶楽部というショートドラマクリエイター集団は、株式会社セプテーニとブランデッドコンテンツを作る事業を開始しました。セプテーニがごっこ倶楽部に出資するという流れです。
山田: その座組は面白いですね。
阿部: ごっこ倶楽部を運営している株式会社GOKKOが2億円の資金調達をした、とニュースになっていましたが、それもTikTokというショート動画のフィールドでブランディングに取り組むという流れが注目トピックになっている証拠なのかなと思いました。例えば、遊園地を運営している会社がショートドラマを撮っている集団にお金を払うからここで撮ってください、と依頼して撮影してもらい、それが世に発信されたら、色々な人の目に触れる。それはもしかしたら、遊園地の紹介動画を作るよりも効果がある可能性もある。
山田: 秒数が短くなればなるほど余白がなくなっていきますよね。CM然り、15秒しかないからこそ要素を詰め込む。長編映像だとしても、拘りだけが強いと押し切ろうとするような作品になってしまう可能性が高い。最短編でも余白があることが、ショート動画の長所だと思います。
阿部: 敢えて素人が撮影したように見せるというか。
山田: そうともいえますよね。TikTokやYoutubeのショート動画で企業とかクリエーティブブティックがその余白を詰めるように設計して、結果CMに逆戻りしたら元も子もない。より良くメッセージを伝えるため、プロの手が加えたとしても、余白を残したままショート動画を作ることがチャレンジなのかなと思いました。
阿部: SNS自体もいずれ時代遅れになると思うけれど、今の世代にとってそれがリアルだから、リアルっぽい映像を見せるからこそ、共感を生む。拘りすぎていない余白がある映像を作るのも強さになりますよね。
汐田: ショート動画の市場も少しずつ変わってきています。先ほど15秒程という話がありましたが、以前はTikTokで伸びた動画の平均の再生時間が30秒くらいだったのに対して、去年くらいから60〜70秒くらいになって時間が延びているのです。投稿者がTikTokで収益を得られる条件も、最低一分以上の動画と設定されている。これまでTikTokの中では少数派とされていた一分以上の動画に対して、明らかにプラットフォーム側も優位性を与えようとしています。それを踏まえると10〜15秒のショート動画とはまた違う流れが起きそうな予感がします。
阿部: 徐々に物語の時代になってきていますよね。ただそれでも、すべてが数値化されることで、それだけで判断されてしまうことがあります。話題性を見る尺度にはなります。しかしその尺度だけだと、本当に深く共感されている長編の映画を、動員数だけを見て見逃すことになる。
山田: 一人の共感の深さは測れないですからね。何万人に見られた映像、と数字だけが独り歩きしてしまう。一人が映像を見た時に、どれだけ共感したか、が重要にも拘らず。 阿部: そうなんですよね。そこがブランデッドムービーとSNSの難しいところです。ただ名前を知って欲しいだけであったら、やはりCMが強い。しかし、企業に共感して欲しい、友達作ろうというミッションなので、深さが重要です。


ブランディングと映像の交差に纏わる人々、彼らの未来
――ブランディングと映像が掛け合わさるまでに、どのような立ち位置の人々がどのように合わさることで生まれるのか。
阿部: 弊社では、企業側のブランディングメッセージをどのようにストーリーにしていくか、プロデュースをビジュアルボイスが手がけ、その先は監督、制作チームをアサインして作り上げていく。映画制作の流れと同じです。
山田: 本来であれば、広告的な映像チームが作る映像を、映画を作るチームが作っているという意味では特殊ですよね。
阿部: それはあるかもしれませんね。そこは弊社が拘っている部分で、映画監督がブランデッドムービーを作り、所謂プロモーションの領域に留まらない。
汐田: 山田さんとの仕事では、複数の専門領域を持つプロデューサーが複数人協業することが特徴的でした。PRONIのブランディングムービーを作る過程では、想定するカスタマージャーニーが明確にあって、どういう人間が主人公で、どのようなシチュエーションを作るか、意見を十分に議論してから脚本家やカメラマンなどをアサインしていきました。僕のように、プロダクションする観点から見ても、目標が一言のタグラインで明確だったので、現場の全員で達成してできるかに尽きます。そのようなプロデュースをする僕と、ブランディングとしての映像のゴールだけを愚直に追うプロデューサー、そして山田さんのような多くのブランドアクションの内の一つとして映像を見るプロデューサー、そうした交差がありました。
山田: 汐田さんとご一緒したPRONIのプロジェクト然り、どうすれば作れるか、ではなく、ブランドのクライテリアを、誰と形を作るべきか、と考えるので、肩書きの不足や見た目の重なりは考えず、同じクライテリアで確かに会話できる人を、必要なだけ集める。PRONIのブランデッドムービーの現場では、自分が理想としていた現場の光景がそこにありました。そこにはクライテリアだけが落ちていて、それぞれがプロフェッショナルな職能で解釈し、最適に行動を重ねていく。こういうことを伝えたい、というメッセージだけが共通にあって、クライテリアだけが転がっていく。そのような現場に、マイクロマネジメントは不要です。結果、クオリティも高かったと思います。

――未来に向かう際、映像という表現はどこに向かい、変化していくと思うか?
山田: ブランディングに関して言えば、ただ顧客に媚びるのでも、論理的に自分たちの伝えたいことを盛り込むのでも、不誠実です。自分たちの伝えたいことを伝えているのに、共感をゴールとする、という難題に、日々の会議や判断で向き合うことができれば、映画的な映像は、ブランディングの新しいスタンダードになると思います。
汐田: 現実に近づいている作品が増えているので、その境目が益々なくなっているからこそ、原始的、原理的で素朴なものが大事にされたら良いな、と思います。
阿部: 海外では、VR、AR、メタバースを駆使したクオリティの高いライブも開催されている。映画の本質の一つは最新の技術でもあると思います。それと交差することで新たなコミュニティができるのではないかとも思います。