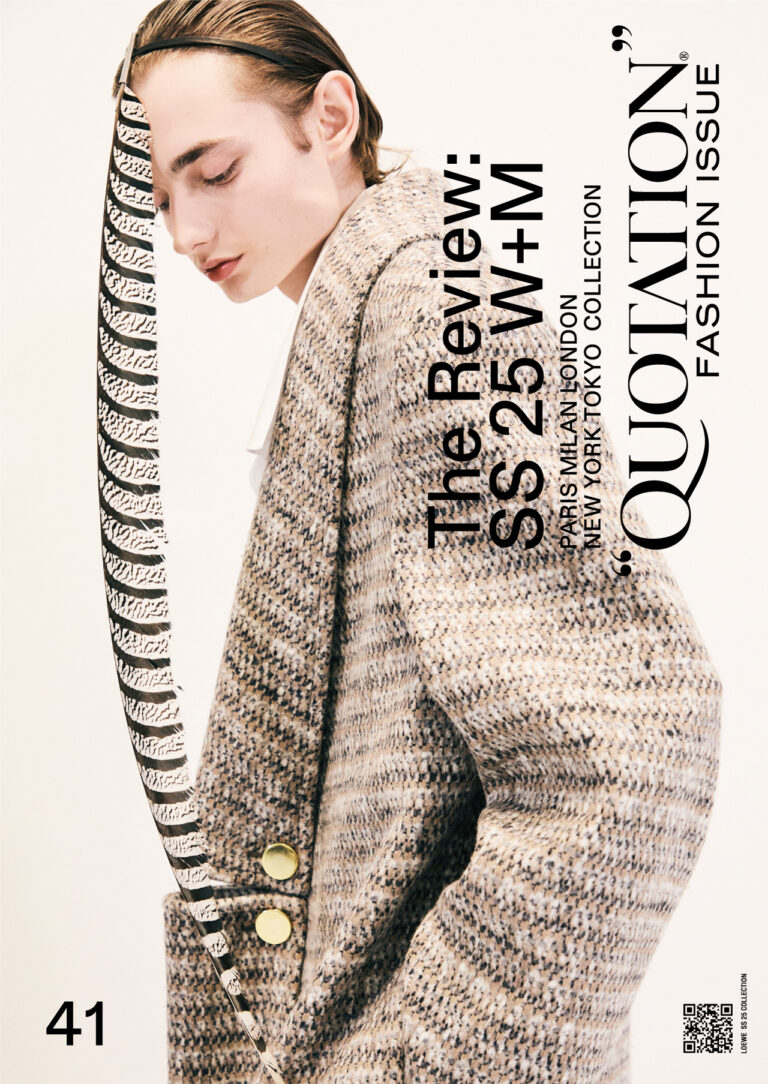KAZE TO ROCK|SPECIAL INTERVIEW WITH MICHIHIKO YANAI ABOUT KAZE TO ROCK SUPERAREA
2024年3月30日、31日にさいたまスーパーアリーナにて、「風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ」が開催される。本イベントは、「風とロック」の主宰者である箭内道彦の還暦記念企画となっている。様々な名広告を手がけてきたクリエーティブ・ディレクターであり、東京藝術大学の教授として若い世代の教育にも勤しみ、時にはアーティストとしてステージにも立つ。筆者は、そんな箭内の実態を掴めずにいた。

箭内道彦
都内にある「風とロック」の事務所を訪れるとマスクをして徹底的に体調管理をする箭内の姿があった。「いやあ、ここまで来ると体調管理だけですよ」と笑みを浮かべる表情からは自身が一番このイベントを楽しみにしており、当日が待ち切れない少年のようにも感じる。そう、この少年性と好奇心が本質にあり、それがすべてとも思う。このイベントでは、ある種異端児のように見られてきた箭内の素の姿を垣間見えるかもしれない。本番を10日後に控える中で、自身に纏わる「いま」を語ってもらった。
厭気を感じていた誕生日とふるさとへの思い
――還暦おめでとうございます。このような節目は気にするタイプか?それとも只の通過点?
ありがとうございます。そうですね、そもそも自分の誕生日を好むタイプではなかったと思います。サプライズも苦手で、正しく通過点に過ぎないと思っていました。しかしある時、福山雅治さんに「サプライズに驚いてあげるのも大人ですよ」と諭されまして。誕生日は自分のためではなく、いつも助けてくれる人や周りの人に感謝する日だと思うようになってからは、雪解けしていくように受け入れることができました。今回のイベントに関しては、還暦パーティーを自分主催で行なう訳ではありません。60代は自由でもあり難しくもあり、試される10年と思っています。何か無茶なチャレンジをしなきゃなっていう気概の表出であって、お祝いではありません。構想的に1年弱。会場はさいたまスーパーアリーナだなと直感していた頃、GLAYのTAKUROさんとご飯食べている時に「一緒に何か面白いことやりたいですね」という話になり、托言付けやすいのは還暦かなとも思っていた、といった経緯です。
――「風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ “FURUSATO”」というタイトルはいつ頃?
昨年の秋頃でしょうか。その時は、ラインアップがまだ決まっていなくて、それをテーマに声をかけていきました。ウェブサイトのイントロダクションにも記載していますが、さいたまスーパーアリーナでなければいけなかった。この場所は2011年3月の東日本大震災時に、福島県双葉町の皆さまの避難所になった。そこで音を奏でて、ふるさとを思い合うという明確なコンセプトがありました。それを軸とした時に、ふるさとといえばこの人だろう、と。僕の友人たちから順にお声をかけていきました。



――自身にとって「ふるさと」とは?
若い頃はふるさとに背を向け、距離を置いていたといいますか。自分の中で折り合いがつかないことをふるさとのせいにしていた時期もありました。例えば、僕は東京藝術大学に入るために3年浪人したのですが、当時の田舎では色々と顰蹙を買いました。「親に迷惑ばかりかけてないでちゃんと働け」「もう受からないから帰って来い」など散々いわれました(笑)。そういう人たちのある種の優しさから逃げたくて背を向けていた。2007年に、サンボマスターの山口隆とふたりで「ままどおるズ」を結成して、『福島には帰らない』という曲を作って歌っているうちに、ふるさとと向き合うようになっていった。2010年にまた福山さんと話をしていて。「ふるさとのせいにしている自分への苛立ちじゃないですか?」と。その時、福山さんが長崎県の稲佐山で大きなコンサートをやって、福山さんのふるさとに全国から人が集まってきて。ふるさととのこういう向き合い方もあるんだなと考えさられた時期でもありました。「猪苗代湖ズ」というバンドを結成したのもこの頃。こうして捉え方も徐々に変わっていった中で東日本大震災が起きて、ふるさとが大怪我をして。そういう時に悪口ばかり言ってた男が何もしないなんて一番カッコ悪いじゃないですか。その年の9月に福島県を西から東へ移動する6日間のロックフェス「LIVE福島 風とロックSUPER野馬追」を3万人規模で開催したり、紅白歌合戦にも出たりなど色々と動いた後に、風とロックで「風とロック LIVE福島 CARAVAN日本」という全国ツアーをしました。その中には、沖縄、神戸、広島、長崎といった大きな苦難を乗り越えた土地、先輩たちですよね。そこを巡って、復興に向けてのこれからのヒントを頂こうと。広島、長崎に行った時のことです。「平和」というキーワードを掲げて世界中にメッセージを届ける、その意味が改めて響いて。いまでは有り触れた言葉ではあるけれども、その意味を考える大切さを痛感しました。それと同時に、福島にとって「平和」に当たる言葉は何だろう、という宿題をもらったように感じて。それが長年に渡って考え続けてきた「ふるさと」だったのです。福島からふるさとの大切さ、難しさ、ありのままを全て発信すべきではないないか、と。色々な変遷を経て、その言葉に再度、結実していきました。
ラベルを剥がすことで見えてくる愛情と少年心
――本イベントではフォーク、落語、アイドルなど日本固有の文化やエンターテイメント性を背景に持つアーティストが揃っている。自身が拘ってきたことが結晶となっていると感じさせるが?
正しく、僕は洋楽にあまり影響を受けていない人間でして。自分が使っている言語で伝えている音楽がスッと身体に入ってくる。どんなにメロディーが良くても詞が良くなければ聞きません。そういう意味では、ご出演頂く方々は、固有の音楽を持っていますよね。只、見る人が見れば、偏った人選だろうし、極端だなと感じる人もいると思いますが、僕の中では出てくれる人たちには共通していて、しっくり来ています。ある意味、僕自身のベストセレクションアルバムを作っている感覚かもしれません。さだまさしさんとBRAHMANの接点は何もないと思われているかもしれませんが、両者の伝え方、信念、スタイルは重なるし、乃木坂46とサンボマスターの対バンも「なんで?」と思う人もいるかもしれませんが、メッセージや熱量はほとんど変わらない。それぞれのファンが見た時にスッと受け入れられると思います。何よりそれが実現している現場を僕が見たい(笑)。


――欧米では1990年代の日本のシティーポップが時流になっていた時期もあったが、それに対してどのように感じているか?
こういう現象は今までもありましたよね。あまり核心を得ていませんが、先入観がない、というのはあるかもしれません。先入観を持っていると、良いものに出会いづらいのです。昨今のデジタル社会における検索文化も然り、自分専用の狭い世界をカスタマイズされてしまうため、その狭き門を通過したものだけしか耳や目に入らない、そういう文化の受け入れられ方になってしまっている。若い世代が「写ルンです」に夢中になった現象は、先入観なく手元に入っていった良い事例だったと思います。ただ、カルチャーにおける先入観、レッテル、ラベリングは未だ根強いかもしれませんね。そこから自由になっているアーティストの真の姿を自分の目で確かめたいというのもこのイベントの企画意図です。好きなものを公言しにくい時代もあった中で、今は随分と声に出して好きといえるようになりました。恰好良いと恰好悪い、明るいと暗い、怖いと可愛い。僕らの世代が余計なセルフラベリングをやりすぎたせいでもあると自省の意も。来場される皆さまがそれを共有できるキッカケになったら良いですよね。あとは、みんな愛のある人たち。福島を思いやるスリーマンの対バン形式もあるし、ふるさとや人に愛を持っているし、そのことに照れがない。サンボマスターもそうだし、乃木坂46もそうだと思います。愛の人たちです。
――異なる要素を重ねることで生じる化学反応にクリエーティビティーを感じるような好奇心旺盛な少年性を思わせるが、いまの自身にとってのクリエーティブとは?
あくまでも個人的な見解ですが、人間の人生は10代で完結すると思っている節があって。20歳を過ぎたらその後は長い長いアンコールのような気持ちです。つまり、10代で好きになったものから逃れることができない。そういう意味では10代の自分と並走して仕事をしている感覚です。或る人はそれを厨二病というかもしれませんが、それとはまた違っていて。10代の自分を形成したものを大事にし続けている。クリエーティブとは、二つの違う要素が重なることで第三の答えが生まれたり、新しい表現や色になることが根幹にあると思います。あとは、初期衝動。どうしてもやりたいと思ったことを諦められないその状態、有り様も少年的ですよね。大人になったことで経験とノウハウが付いて、少年が思い浮かべていたイメージを実現させている状態。『月刊 風とロック』も、売り物じゃないから誰にも文句は言わせない、という名目で発行していたのですが、僕は、金持ち中学生のスクラップブックと呼称していました。好きなものだけを掲載し、この年齢だから撮り下ろしでスクラップできている。だから若い人から見たら全く別の感覚に見えているかもしれないし、異質に思うかもしれませんが、その化学反応に対するリアクションを楽しみたい。今回のイベントは、異種格闘技戦といいますか。仮面ライダーとウルトラマンが同じステージにいるところを見てみたかったではないですか。どっちが勝つんだろう、どのような合体技を披露してくれるのだろう。僕にとっての対バンとはそういうスタイルを指します。

「月刊 風とロック」2014年12月号

「月刊 風とロック」2013年5月号
――アウトプットが終わると、それに浸る時間が多い?それともすぐに反省点や次なるステップが思い浮かぶ?
反省はあまりしません。思いに耽ることはありますね。その中で、また次やるべきことが自分の中で少しだけ光が差してきたりもする。次にやるべきことを見据えるために今できる全てをそこで使い切ってしまいます。
――それは前日の準備、本番当日、全てが終わった後なのか、その感覚はいつ訪れるのか?
その3つのタイミングで1/3ずつ訪れます。前日で見えてくるものもあるし、本番中にしか感じ得ないこともあるし、終わるまでわからない感覚もある。何が成功で何が失敗かも明確ではありません。化学反応が大化けすることが成功とも限らない。AとBが向き合ってCにならなくても愛おしく感じることもあるのです。異質なもの同士がどのように溶け合い、向き合うのか。それは現代における人類への宿題でもあると思います。さいたまスーパーアリーナでは、これからの自分や世の中にとってのチャンスやヒントが見つかったらいいなと思います。次なる未来では、勝ち負けの二元論ばかりではなく、第三の答えをどのように出すかが求められると思います。大学の講義で、アートとは、デザインとは、クリエーティブとは何かと聞かれることが屡々あります。ある街に壁があって、それを街の人たちで何色に染めるか、揉めたとします。赤色が良いとか、黄色が良いとか、議論が平行線になった時に多数決で決めると負けた方は気持ちよく受け入れることはできません。今までだったら、赤と黄を混ぜて橙色にしよう、という案を出すことが解決策のひとつだったのですが、じゃあ水色はどうですか?とか、そもそもその壁って必要なのかと提案できることもクリエーティブになり得る。それらとこういうイベントの本質は地続きで繋がっています。

「月刊 風とロック」113号より
安全圏からの脱却、広告マンとしての矜持、そして未来
――自信を安全圏に置いておかないように感じるが、安心を感じるとそこから脱却したくなる?
さいたまスーパーアリーナを選んでいる時点でそれは否めませんね。あの規模感はリスクがありますから。ライブハウスやもう少しキャパシティーの狭いホールやアリーナでも良いのに、色々な規制や予算もかかる場所をわざわざ選んでいるのだもの。ジャンルやカテゴリー、肩書きではなく、その姿勢が伝われば良いなと思います。
――「風とロック」は一会社にカテゴライズされることなく、番組であり、プロジェクトであり、集合体であり、プラットフォームでもあるが、自身はどのように捉えているか?
僕は広告という仕事を生業にしています。「もう広告作っていないんですか?」とたまに聞かれますが、僕としては今でも作り続けている。自分にとっての広告とは、対象を応援することであり、対象の魅力を抽出して最大化させることです。だから、番組を企画したり、イベントを敢行したり、フリーペーパーを作っても全て広告なのです。不器用に一つのことしかやっていない。例えば、「NO MUSIC NO LIFE.」を初めて世に出した時はそこまで強い言葉ではなかったのですが、たくさんのアーティストや音楽を愛する人たちがあの言葉を育て、力を与えてくれた。「風とロック」も然り、面白がってくれている人たちが、色々な景色を見せてくれています。このスリリングでピースフル、様々な流動性を持つ集合体には大勢の仲間たちがいます。自分もその中の一人です。
――21年目をひた走る「風とロック」だが、今後どのような未来を見据えているか?
特に見据えていないんですよね。見据えると柔軟性が欠けてしまう気がして。漂流しているうちにやるべきことに出会って、じゃあそれをどう実行するかを繰り返してきたので、計画性も展望も特にないのです。この仕事は求められてマッチングして前に進むことができる。これから迎える60代の自分を社会はどのように必要としてくれるのか。蓋を開けてみないとわかりません。幾つになろうが、インテリジェンスと美意識と時代感覚があれば作り続けることができます。60歳を迎え、自分がどのように衰えていいくのか、進化していくのか。そこに期待しています。死ぬまでこの仕事をやるとか、今日で辞めようとかは簡単にいえる話ではありません。60代の走り方を知りたくてこのイベントをやるのかもしれません。これで終わりかもしれないし、加速するかもしれない。そんな年齢になったのです。開催前なので、こういうことがいえているのかもしれませんね。あまり恐怖感を感じないように、詳しく考えないようにしているけれど、スリルが隣にずっとある感覚は悪くありませんよ。