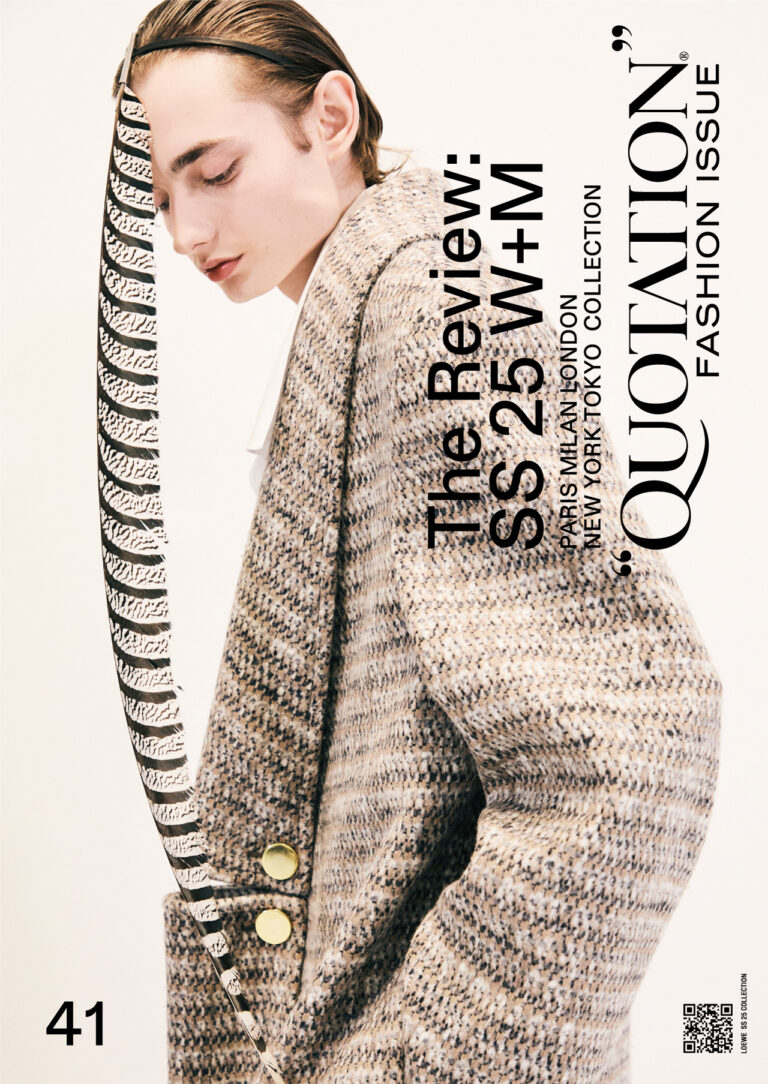- 1 新しいデジタル技術が登場する今、その影響はアートの世界にも広がっている。美術家・三澤亮介は、デジタルとアナログを融合した方法でこれまでにないビジュアルを作り出し、人々を惹きつけてきた。美術家に転身し、瞬く間にアート界の階段を駆け上がる彼の創作はどのように始まり、またどのように進んでいるのか。3月25日に始まったアーティスト公募企画「TYPELESS」にて、渋谷パブリックアートプロジェクト「YOU FEEL」に参加する三澤。そのプロジェクトを企画したEmbedded Blue Inc.代表の片岡 奨とともに、これまでの創作や今回のプロジェクトについて語ってもらった。
- 2 美術家としての始まり
- 3 これまでの歩みと制作における葛藤
- 4 海外に広がる活動の幅
- 5 AIとの共作
- 6 渋谷パブリックアートプロジェクト「YOU FEEL」とは
- 7 二人の出会い
- 8 これからのアート業界に巻き起こす新風
- 9 時代を反映する通訳であり、媒介者である現代アート作家
新しいデジタル技術が登場する今、その影響はアートの世界にも広がっている。美術家・三澤亮介は、デジタルとアナログを融合した方法でこれまでにないビジュアルを作り出し、人々を惹きつけてきた。美術家に転身し、瞬く間にアート界の階段を駆け上がる彼の創作はどのように始まり、またどのように進んでいるのか。3月25日に始まったアーティスト公募企画「TYPELESS」にて、渋谷パブリックアートプロジェクト「YOU FEEL」に参加する三澤。そのプロジェクトを企画したEmbedded Blue Inc.代表の片岡 奨とともに、これまでの創作や今回のプロジェクトについて語ってもらった。

美術家としての始まり
――フォトグラファーから美術家に転身された経緯について教えてください。
三澤:もともと自由になりたいという欲求があって。もう少し遡って話すと、大学の映像学科を出てから広告会社のサラリーマンだったんです。でもその会社員時代から、自由に何かを作りたいとか、社会のしがらみから逃げたいという気持ちがあって。その行きつく先がアーティストっていう括りになっていたんだろうなと、今振り返ると思いますね。
――その自由とは、精神的な自由ですか?それとも身体的な自由?
三澤:両方あるんですけど、多分精神的な方が大きくて。制約の中で何かをしたくないとか、自分で作ったルールで勝負したいとなると、もうアートしかなかったという感じですね。

――もともと絵は苦手な方だったとお伺いしたのですが?
三澤:今も苦手です。厳密に言うと、今も特段絵を描いている、という意識はないです。僕が取り組んでいるのは、デジタルソフトやAIといった新しい技術やテクノロジーを駆使してビジュアルを作ること。僕は絵の美術教育を受けていない分、自分の使えるソフトとオリジナルの手法を用いてビジュアルを作っています。そこにコンセプトとフィロソフィーを詰め込んでるので。そういった意味で、美術家でアーティストではあるけど、今でも絵は苦手です。
――そうなんですね。でもそれが作品の特色になって、これまでにない新しいアート作品が生まれていますよね。
三澤:こういうビジュアルを作っている人は他にいないんです。かつ、僕は自身の生み出した手法でしか作品を作れないという、特殊で限定された人間です。だからこそ、限られた要素の中で発揮できる力を重ねたような、新しいゲームを一人でやっているような、そんな認識なんです。偶然に偶然が重なって辿り着いたという感じでした。
――その偶然が重なって、オリジナリティーとして確立されているということですね。
三澤:そうですね。オリジナリティーやセンスとかって、後天的なものじゃないんですよ。絵が描ける人って、基本的に最初から描けるんです。誰でも練習したらある程度は描けますよ。僕もデッサンは習っているから描けるけど、最初からできる人はやっぱり飛び抜けているんですよね。
でも僕は絵は苦手だけど、今と同じようなスタイルの作品は最初から作れたんです。自分のやってる手法はかなりの発見で、発明だと思って。だからこれができた時に、「あ、もうこれは天才だ」、「時代変えられるな」みたいな。これが認められたら、自分のニューエラが来るって感じましたね。
――最初の瞬間からビビっときたんですね。
三澤:きましたね。

これまでの歩みと制作における葛藤
――美術家として数年でここまで注目されていますが、それは早いと感じますか?
三澤:美術業界でいったら異常な速さだと思っていて。予備校に通って、美術学校に通った後にデビューするのが普通だと思うので。そこから考えるとゼロベースの人間が3年、4年で注目されるのは早いと思います。
ちょうど一昨日まで「アートフェア東京」が開催されていたんですけど、日本のアーティストで参加できるのは、多分200名とか300名くらいしかいないんです。そこに自分が入れるのは異例なことだと思っていて。それは美術業界で考えたらすごくイレギュラーなことですよね。その他にも、ロンドンの大手ギャラリーから直接コンタクトがあって所属出来ることになったり。日本に所属ギャラリーを持たないまま海外に行くのも珍しい動きだと思います。
――制作の中で迷いとか、こうした方が良かったなとか、こうしていくべきだなとか考えることは多いですか?
三澤:ありすぎるくらい多いです。普段embededd blueチームの方たちとコミュニケーションをとるんですけど、多分みんなもこんなに話変わる人いないって思ってると思います。翌日には話が変わってたりとか、その日の朝言ったことが夜には変わることもざらにあるので。それはもう迷ってる時ですね。迷ってない時はそんなことないんですが。

海外に広がる活動の幅
――2022年は台湾、2023年はギリシャやニューヨークなど、海外でも活躍されてますよね。世界からも注目されつつあるということは実感しますか?
三澤:まだまだだとは思うんですけど、チャンスは十分いただいてるなっていう気はしています。海外でも頑張っていきたいなと思ってます。
挑戦したい場所はたくさんあるんですが、言語の壁とか、コミュニケーション、あとは自分のコンセプトを多言語で伝えていくことが難しいですよね。昨今のアーティストにはそれが非常に求められていると思っていて。有名なアーティストだと周りに完璧な翻訳者とかネイティブの人がいて、いろんな言語に訳して説明してくれますが、そこまではいかなくても、まず自分の作品を見た海外の人が、言語のない状態で作品を気に入って、コンセプトを伝えた時にそれが面白いなと思ってもらえるところまで頑張りたいなと思います。
――次に挑戦したい国はありますか?
三澤:そうですね、それは自分の今後の目標と結びつくのですが、やはり海外で制作をしてみたい気持ちはずっとあって。半年でも一年でも、滞在して制作をして展示することをしてみたいです。美術が有名で栄えている国というよりは、自分が呼ばれてる気がする場所でやってみたいと思います。
――そこに住むからこそ、その国の文化を感じて作れるものがあったり?
三澤:文化ももちろんあると思うんですが、自分はずっと日本にいるので、日本から離れた時に何を感じるんだろうと思って。何か自分の中で予期しない変化があるのかということを確かめてみたいです。
AIとの共作

――今回の「YOU FEEL」で展示される作品は?
三澤:デジタルソフトの中で、自身が描いた絵の中にAIに提案させる箇所を作り出し、そのAIからの提案を取捨選択し、その分岐の中からさらに次の提案を求めていく。AIと自身のラリーのような形で作品を制作しています。このビジュアルに関しては、人間の画像を解体して作っていて。画像データの中の人間の四肢を壊したものと、人間の衣服をAIに作らせて上に配置して、新しいビジュアルを作っているんです。

渋谷パブリックアートプロジェクト「YOU FEEL」とは
――今回のパブリックアートプロジェクト「YOU FEEL」はどのように始まったのでしょうか?
片岡:去年の秋口くらいに、渋谷駅前エリアマネジメントさんが主催する駅の周りの環境美化をテーマにした「TYPELESS」という企画の公募があったんです。公共空間を開放することでアーティストに機会を与えて、キュレーターもしくはアーティストの応募の中から企画を採用する形式なのですが、それに応募するための企画を作ったのがスタートでした。

――今回4名アーティストの方が参加されていますが、それはどのように決定されたのですか?
片岡:渋谷という街を背景に、そこに重ねるアーティストのスタイルと作品をイメージしながら企画と作家選定について考えました。今回の4名については、時代やカルチャー、デジタルとアナログといったメディアや領域を横断し、新しい価値観や概念を提示するような作家さんであることが共通点だと思います。
――三澤さんの場合は、デジタルとアナログの横断でもありますね。
片岡:そうですね。特に、彼の場合はすごくいろんな軸で領域を横断し、その境界をさらに新しいものに見せていく。デジタルとアナログでもそうですし、時間軸の横断でもあって。今までにない既存の価値観とか概念をアップデートしているなと思います。
二人の出会い
――三澤さんの作品を最初にご覧になった時、どのような印象を受けましたか?
片岡:シンプルにかっこいいなと思って。実はこうやって一緒に仕事をするようになる一年くらい前、まだ面識も無い頃に、個人的に作品を購入していたんです。三澤さんは人の心を掴むビジュアルをこれまでも多く生み出してきました。一目見た時に視覚的に新しいと感じるものや、本能的に魅力的に感じるものを作り出す才能を最初に感じたのをよく覚えています。
三澤:最初に僕が知り合いを経由して片岡君と繋がった時に、僕の作品を持っていたのと、一番最初の個展を観にきてくれていたという背景があって、一緒に仕事することに対して、信用することができました。

これからのアート業界に巻き起こす新風
――新しい作風やマネジメントスタイルで、これからどのような活動をしていきたいですか?
片岡:どういうポジションで何をしていくか、それはアーティストの生き方であり、評価の一部です。僕らは“社会の中にある”アートという視点を忘れずにいようと思っています。アート以外の業界との関わりだったり、今、社会が直面している事態や潮流に対して、アート業界で生きている自分たちに何ができるかを考える。作品の価値や、販売をすることだけを考えるのでは、世の中は変わらない。社会的な意義や問いを持つことの方が絶対に本質的です。
三澤:旧体制のままでは絶対に変わらないと思います。アート業界は学歴主義で権威主義のところがあって、村みたいな場所なので。そういう場所に対して、僕や片岡君で新しい風を吹かすことができるはずです。それに対して反発される方々もたくさんいると思うんですよ。でも3年、5年と時がたてば、こちら側がメジャーになって時代が変わるんじゃないかなと個人的には思います。

時代を反映する通訳であり、媒介者である現代アート作家
――AIをはじめ、どんどん新しいものが出ているなか、新しい技術を使ったアート作品も出てくるわけで。それに比例してアート界の体制が刷新されていくのは必然的にも思えますね。
三澤:時代ですよね。この間、美術評論家で、東京藝術大学名誉教授、金沢21世紀美術館特任館長を歴任されていた秋元雄史先生がセレクションした展示「『秋元雄史セレクション~ブレイク前夜』| ブレイク前夜展in金沢」があって、そこに選定して頂いたんです。秋元先生に僕の作品のことを説明させて頂いた時、面白いって言ってくださって。
その時に秋元先生が「作家はその時代を反映する通訳というか媒介者で、その時代を反映する人だと思う」というお話をされていました。それは、その時代において一番早く何かをキャッチして、美術にそれを反映する必要があるということですよね。それができないと、これまでのものになぞらえた作品になってしまう。それを聞いて、現代アートと定義する以上、その時代を反映したものであるべきだと思いました。
――このプロジェクトを通して、どのようなことを伝えたいですか?
片岡:伝えたいことよりも、そこに存在していることをまず知ってほしいですね。「YOU FEEL」というタイトルを見ると、「感じること=感想」という印象を持たれるかもしれないですが、実際はそうじゃなくて。どちらかというと、そこに存在しているものを知覚するという意味で“FEEL”という単語を使っています。まず、認めることって大事じゃないですか。多様性についての議論において、マイノリティが擁護されるか、攻撃されるかの話ばかりだなって思っていて、それ以前に互いの存在や主張を認めるという前提が本当の多様性の始まりだと思います。それが伝わって初めて、渋谷の街でこの企画をやる意味があると思っています。

プロフィール:
三澤亮介:1992年生まれ。立教大学映像身体学科卒業。美術家。メディアパラドックスという独自の手法を提唱し、アナログ-デジタル、写真/画像データ-絵画を制作の中で横断する。捉えられない時間の経過と人間の実体性を絵画のフォーマットの中で可視化し、自身の経験を投影したヴィジュアル構成を提示することで、固定概念の更新に挑む。作品によって現代に生きる自身の極めてパーソナルな感情や経験と、先人との記憶や時代をクロスオーバーし、普遍的な価値をスタディする機会としている。主な展示に「Tracing the night」(333 gallery 台湾 2023) 、「NOH」(HOFA gallery ギリシャ 2023) 、「Project the Process」(IRRITUM gallery NY 2023)など
片岡 奨:Embedded Blue Inc. 代表取締役/プロデューサー 1992年生まれ、東京出身。野村證券-野村ホールディングス-株式会社N-Village、金融コンサルティング – アプリ開発PdM – 新規事業開発を経て、株式会社Embedded Blueを創業。アート業界におけるリアルビジネスから着手し事業を展開している。法人営業での複数の大型ディールクローズ、海外での事業開発、アプリ開発、新規事業立ち上げ等の経験をアートシーンに持ち込み、ビジネスとクリエイティブ双方の現場で事業開発、プロデュース、プロジェクトマネジメントを手がける。 アート&プロジェクトマネジメント講座 第2期 修了(監修:南條史生(N&A株式会社代表、森美術館特別顧問)、諏訪光洋(株式会社ロフトワーク代表)