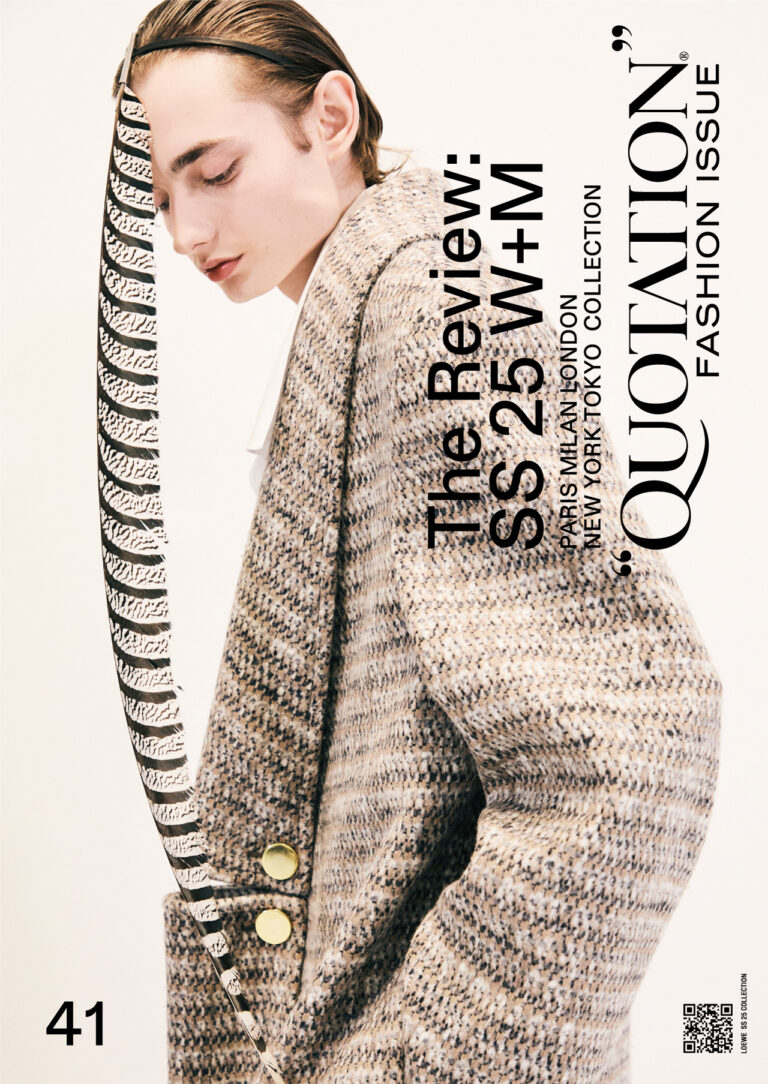FEATURE|デザインとビジネスの融合。コンビニエンスウェアのアートディレクター・安田昂弘へインタビュー vol.2

クリエイティブディレクター・落合宏理さんとの仕事
――クリエイティブディレクターの落合さんとは、どのようにお仕事されているんですか?
プロジェクトの動きが激しいので、毎週定例会があります。作ったパッケージのラフやチームで考えた商品名、コピーなどの確認をしてもらったり、新商品の店頭展開や撮影プランなどについて打ち合わせをしています。
あとはコラボものの商品に関しても相談させてもらうことが多いですね。その世界観によって、今回はどういうパッケージで行こうか、みたいなことを提案させて頂いています。
でも基本的にはすでに展開しやすいフォーマットができてるので、そこにどんどん当てはめていきながら進めています。落合さんには最終チェックをして頂いて、各所アプルーバルが確認が取れてから進めていくような感じです。
これまでを通して
――これまでのシーズンを通しての反応はいかがですか?
ソックスだけでも、累計1600万足売れているんですね。また、昨年は「ファミフェス」でファッションショーを開催して様々なメディアに露出したり、結構認知されてきたのかなって思ってたんですよ。ですが、この間コンビニエンスウェアのスウェットが、SNSのレビューなどでバズり、2000万ビューくらい行ったことがありまして。その影響なのか、その後数日で全国のファミマからスウェットが売り切れるっていう。その時に調べてたら「コンビニエンスウェアって何?」とか、スポーツウェアという言葉のように、コンビニに行く格好のことをコンビニエンスウェアだと思っている人がいたりとか。知らない人がたくさんいるのを実感して、まだ全然浸透してないんだっていう感覚になったんですね。 みんな目的を持ってコンビニへ買い物に行くんだけど、興味ないと素通りするじゃないですか。例えばコンビニに糸楊枝や布ガムテープって売ってたっけとか、毎日通ってるはずでも売っているかどうか全く分からないものってあると思うんですよ。それと同じように、興味ない人からしたらまだ素通りされている商品なので、どうやってより認知を広げていくのかは、課題としてはあるよねってよく話しています。

コンビニならではのアートディレクション
――コンビニにおいてのパッケージデザインと、他のアートディレクションとの違いはありますか?
コンビニはお客さんのモチベーションがバラバラですよね。時間を潰しに入ってくる人もいれば、お昼ご飯買いに来る人、トイレだけ借りに来る人もがいたり。普通のアートディレクションだと、もうちょっとターゲットの想像がしやすいですね。想像しやすいが故に新しいことを打ち出すのは難しかったりもするんですが。
コンビニに関しては、より社会の人たちが何を考えてるかを意識しないといけないです。よく自分は普通だと思っていても、普通の人なんか一人もいないよね、みたいなベタな会話があると思うんですけど、 みんながそれぞれ普通だと思ってることのど真ん中を見つけて、そこからデザインを広げていくことが大事なポイントだと思っています。

Retoucher: Akira Takeuchi (UN)
かっこよすぎてもダサすぎてもいけないし、おしゃれすぎてもおしゃれじゃなさすぎてもいけない。でもみんなが欲しくなるようにデザインしなきゃいけないので、普段のアートディレクションよりもかなり体力を使いますね。
シーズンビジュアル一つとってもそうです。例えば高年齢の女性の方のモデルさんが見つからなかったり。でも、一番知って欲しかったり買ってほしいのってその層の方々だし、そういう人たちに「なんか若い人向けのものやってるわ」と思われないように考えていくと、やはりファンが明確なアートディレクションよりも、難易度が高い印象があります。
「透明人間」として最高のブランディングをする
――ブランディングにおいて大切なことは何だと思いますか?
今までデザインしてきたスポーツ産業や音楽産業、エンターテイメントなどの仕事は、ユーザーやファンが明確で、その世界観が好きな人たちに向けてデザインしたり、企画を考えていくことが多かったんです。でもファミマと仕事をし始めてからは、自分の身の回りにいない人とか、想像の範疇を超えてる人がそれを買うということを考えなければいけなくて。様々な人たちが行く場所で売られる物なので、自分の中で「こういうデザインがいいと思う」という考えが、あまり重要ではなくなってきたんです。そんなことよりも、多くの人たちがその物を欲しいと思い、実際に手に取って買ってもらうことのほうが大切なんだと。
今はAmazonなどで商品を買うと翌日には届いたりしますが、手に取って買ってもらう、しかも商品には直接は触れられないっていう条件下でデザインしなければいけない時に、自分らしさを表現することの優先順位がかなり下がったんです。自分がどうしたいかということよりも、お客さんが間違いなく買い物できて、どんな商品ならポジティブに買いたくなるのか、間違えないか、商品パッケージを捨てるのを躊躇するのかなど、最低限の条件を積み上げていって、それをしっかり整理したところで現在のデザインになりました。

Retoucher: Akira Takeuchi (UN)

Retoucher : Naomi Sakurai, Hideaki Nemoto
最低限のことを最低限しっかり恥ずかしくないレベルで組み上げていった結果、とても自分らしくなったと思っているんですよ。そんな風にブランディングを進めていった結果、最終的に見た時にちゃんと自分が作ったものっぽくなっていたのは面白い体験でした。「あれ安田さんのデザインでしょ?」みたいな話をよくされたり。今までの取り組みとは異なる、ブランディングの違う体験をしたような感じがしました。
――デザインすることについて、少し意識することが変わってきたということですか?
アートディレクターってどうしても自分の爪跡を残したがるんですよね。ベーシックですが、目線の誘導をどう組んでいくかとか、機能に目が届くような順番の設計だったり、ちゃんと中身を見せたり、店頭で見た時の新しさを感じさせたり、ブランディングを徹底していくことの方がよほどストレスもかかるし、難しい仕事になります。パッケージが全然商品と関係ないビビッドな色で塗られてたりすると、それは嘘のコミュニケーションになってしまいますよね。それよりも商品自体がアイデンティティだから、その商品が自然と強くなれば面も明るくなるし、自然と物も売れるはずです。買う人も面白い、かわいい、かっこいい、こういうのが欲しいという感情から手に取ってくれるのではないかと考えているので、いかに“透明人間として”ブランディングするべきなのかということを今回は考えました。

――客観的にコンビニエンスウェアは成功している印象があるのですが、その理由は何だと思いますか?
大学時代に先生方から言われたことを思いだすことがあって。それは、声を大にして言わなきゃいけないことや一番伝えなきゃいけないことを、わざわざ細い書体にして読みづらい文字にしたり、文字サイズが大きくてもコミュニケーションが弱かったりするのは、それがいくらおしゃれに見えても無意味だ、ということです。ちゃんと声が大きいものは声の大きさに比例して届けるべきだという事を、本当にそのままやったんですよ。しっかり大きく、伝えなきゃいけないことの順番に沿って大きさを変えていって。基礎の基礎を大切にデザインしたんです。
会社員時代に「何も見ずに普通の大学ノートってデザインできる?」って、アートディレクター の天宅 正(てんたく まさし)さんから言われたんです。どれくらいのピッチで、どんな濃さや太さの線が引かれていて、右上にはなんて書いてあるのか。一般的に、どれが普通か分かるかって。僕はそれを言われた時、結構衝撃的だったんですよ。「自分にしかできないことをやる前に、誰でも見たことがあるものが体に擦り込まれていないと、見たことのない物なんて作れないよね」って言われているのかなと思ったんです。それ以来、割と自由なグラフィックも作るんですけど、しっかりベーシックに文字を組んでいくようにもなりました。

普通のことを普通にコミュニケーションを取っていくことに対して、世の中的にそれがオリジナリティーではないみたいな妙なレッテルや感覚があったように思って。結構みんな避けたがるデザインだと思うんですね。だけどきちんと自分なりに解釈して、そこをもう一回基本通りにやっていったら、しっかりコミュニケーションが取れて、物が良ければもちろん売れるよねっていうことが実証された気がしています。
――「いい素材、いい技術、いいデザイン。」ってことですね。
そうですね。シンプルにストイックに文字を組んでいくことが、結果に繋がってるような気がします。透明なパッケージで、コンビニで大きく展開された時に急に新しいデザインに見えるっていうのが面白いと思って。想像はしていたんですが、いざ実現した時には感動しましたね。なんかちゃんと新しいものを作ることができたなと思って。
先ほども言いましたが、爪痕を残すのはアートディレクターの仕事ではないなってことも思いましたね。それはブランドがちゃんと結果を残すことなので。そこの足がかりになるようにデザインしていくことが僕らの仕事です。結果的に、意図せず“らしさ”が出ていれば、それが結果なので。無理にそれっぽいデザインをすること自体がナンセンスなのではないかと思いますね。プロジェクトを通して、すごく勉強したことです。
このパッケージがかっこいいよねとか、可愛いよねとか、なんか捨てづらいよねって思うような商品を、コンビニのような生活により近いところで一つでも多く作っていくことにデザインの可能性を感じています。

ここから生まれる新たな循環
――これからの目標について教えてください。
商品を買った人が、それをデザインしてる人に興味を持ってくれて、そこからデザインの仕事を目指す人たちが出てくれると良いなと思います。パッケージに興味を持つ人たちもいれば、中の服に興味を持つ人もいるはずですよね。コンビニだけどコンビニエンスウェアのような尖ったことをやっていいんだって思ったら、ここからまた色々なことが循環して、新しい世界観が出てきたりするのではないかと思うんです。
本当に奇跡的に時代のタイミングにはまった気がしているので、それを一時的なもので終わらせるのではなく、新しいことに挑戦し続けたいと思っています。自分がこんなこと言う大人になるとは思わなかったんですが、「デザインでちょっと社会が動くといいな」なんて思ったりしていますね。

安田昂弘 (やすだたかひろ)
1985年生まれ。獅子座。名古屋市出身。
2010年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業後、株式会社ドラフトにデザイナーとして勤務。2015年に同社より独立し、クリエイティブアソシエーション「CEKAI」にアートディレクターとして所属。
ブランディング、アートディレクション、グラフィックデザインを軸に、デジタル領域やプロダクトデザイン、映像、空間などの領域の仕事にも広く携わる。
2015年より自身のグラフィックの新作展示を毎年開催するなど、セルフワークによる国内外での作品制作、発表も行う。身長は190cm。